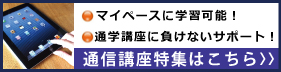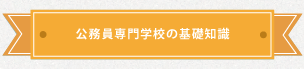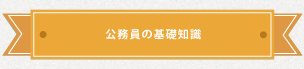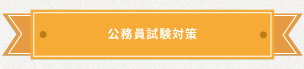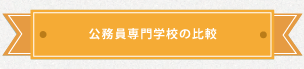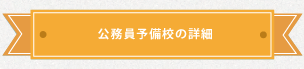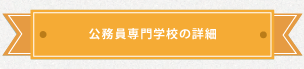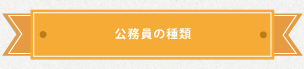公務員試験について

公務員には、国家公務員の中でも総合職と一般職があり、国家公務員以外にも地方公務員など多くの種類があります。
教養試験と面接試験があり、上級・中級・初級に分かれています。よく地方上級という言葉を耳にすると思いますが、公務員試験の受験用語です。いずれにせよ、公務員試験を受けて合格しなければ、公務員になることはできません。
その公務員試験内容、過去問対策および効率の良い学習方法を一緒に見ていきましょう。
公務員試験の基本的な情報

公務員試験の概要
公務員になるには複数回公務員試験に合格しなければなりません。
スケジュールと試験内容を見ていきます。
1次試験の筆記テストとして専門択一、教養択一、論文試験、専門論文試験が行われます。専門記述は一部の試験のみで実施されてます。
1次試験を通過すると、2次試験の人物試験としての個別面接が行われます。質問される内容は、志望理由や自己PRに関係するものです。地方上級や市役所では、集団面接や集団討論を実施されがちです。公務員試験はほぼすべて個別面接でしょう。
2次試験も合格した方は、採用面接である個別面接を行います。受験生の意識確認を取ることが主であり、併願状況やいくつかの試験に合格した際には、どのような進路を選ぶかどうかなど聞かれます。
これだけ見ても、公務員試験に向けての準備時間と過去問対策が必要ということが分かりますね。
また、試験の種類や区分によって受験する際に年齢制限が設けられています。高卒程度の受験可能上限年齢は20代前半程度で、大卒程度の試験だと30歳前後程度が一般的です。
多くの公務員試験は高卒程度、短大・専門卒程度、大卒程度の区分で行われます。これは単に問題の難易度を示すものです。一部の試験では社会人を対象とするものもあります。
あなたが高卒や社会人でも、公務員試験を受験するつもりなら、受験資格があるのかどうかということを事前に確認しておくことをおすすめします。
2021年度の公務員試験受験者人数
2021年度の公務員試験受験者数は前年より2,515人減少しました。5年連続で減少し、前年度は近年で最大の落ち込みでした。
以下は公務員試験の受験者・合格者。それの倍率を表した表です。
| 職種 | 公務員試験 | ||
|---|---|---|---|
| 対象者 | 院卒者 | 大卒 | 高卒 |
| 申込者数 | 1,765名 | 28,521名 | 13,824名 |
| 合格者数 | 501名 | 6,031名 | 3,075名 |
| 合格倍率 | 3.52倍 | 4.73倍 | 4.50倍 |
公務員試験教養と専門問題の内容紹介

それでは、公務員試験はどのような内容が出題されるのか、どのような形式で出題されるのかを過去問をもとに詳しく見ていきましょう。
公務員試験の筆記試験の分野として、教養と専門の2つがあります。
教養科目には、一般知能と一般知識の2つがあります。
公務員試験の内容を1つずつ紹介します。
【一般知能】
数的処理
数学的な思考力や推理力を問う問題です。
初級から上級程度の中学入試的な数学のような問題が出題されます。
文章理解
英語や国語が出題されます。与えられた文章に対して、論理的に理解する能力が求められています。
【一般知識】
人文科学
日本史、世界史、地理、思想、文学や芸術の内容が問われます。
その中でも、日本史では近代史が中心で、テーマ史が頻出となっています。
世界史も近代史が中心で、アメリカ史、アジア史、イギリス史が頻出です。
地理では、自然と人間と世界の地形や気候や土壌が問われます。
思想は、西洋の近代思想と東洋おもに日本の思想が頻出です。
自然科学
化学、生物、物理、地学や数学などの理科と数学に該当する内容が出題されます。
社会科学
政治、法律、経済や社会が出題されます。
政治では、政治制度や政治原理、選挙制度、行政関係、国際関係が問われます。
法律は、法学概論、憲法や民放が出題範囲です。
経済では、マクロ・ミクロ経済、財政、経済事情が出題されます。
社会は、社会学・心理学や社会事情が問われます。
社会科学の中で特に出題されやすい分野は、政治・経済です。
時事
環境問題、社会保障、労働問題や消費者問題といった現代の日本の重大な政策課題が中心に出題されます。時事問題は他の分野と関連付けて出題されることや作文・記述試験や面接対策としても欠かせない分野になっています。
専門科目には、法律系、経済系や行政系があります。
また、理系公務員を目指す方は、土木、建築、農学等の専門科目の過去問を確認するようにしましょう。
公務員試験に合格するには、およそ6~7割程度の得点が必要と言われています。
出題される科目幅が広くすべて完璧にしようとすると非効率的な勉強法になってしまうかもしれません。
以上の教養知識をしっかり身につけて過去問に取り組みましょう。
公務員試験の過去問から出題されやすい傾向を見ていきます。
一般的に出題されやすい過去問テーマ厳選

教養択一試験の足切りのならないように主題されやすいテーマを厳選すると、教養科目では数的論理、判断推理、資料解釈、思想・文学・芸術、経済です。
なぜこのように絞ったのかと言うと過去問から出題されやすい頻度もありますが、他の科目は点数配分が低いためコストパフォーマンスが良くないです。また、過去問を確認すると、せっかく勉強したのに公務員試験で出題されないケースがあるからです。
専門科目では、法律系では憲法・民放・行政法で、経済系では、経済原論・財政学・経済史・経済事情・経済政策・経営学です。
補足をしておくと、思想文学はほとんどの受験生が無視してしまいがちですが、他の科目と比較するとマスターしやすく、ほとんどの公務員試験で3~5点ほど配点されており、ライバルと差をつけやすくなっています。
過去問活用方法
公務員試験の出題内容を知ったところで、過去問対策について解説していきます。
過去問の使い方は、テキストでインプットしたものを過去問でアウトプットします。
過去問には、過去に試験で出題された問題がたくさんあるため、実際の問題を解け、出題範囲も網羅でき、しっかりと教材を活用すれば公務員試験に必要とされているレベルの教養知識を身に付けることができます。
公務員試験は、過去に出題されたものから類似した形で出題されることが大半というのが特徴です。
よって、何年分の過去問を解くことによって、より深い傾向や分析もできるようになるでしょう。
つまり、公務員試験に合格するには、過去問をこなすという作業が大事ということが分かりますね。
ただ単に、問題を解くことをこなすのではなく、理解を重視しましょう。
選択問題は、どこがどのように違うのかをしっかり把握し、間違えた問題に対しては、何がわからなくて正解に至らなかったのかというプロセスを常に持ちながら、過去問を活用しましょう。
その間違えた問題を定期的に繰り返し復習することで、長期記憶にも繋がり、教養知識を定着させることができるでしょう。
公務員試験の教材はAmazonで購入できます。
おすすめの教材は新スーパー過去問ゼミ、過去問350や過去問500です。
この教材は、教養分野を網羅しており、電気、農業、栄養士、福祉、機械、薬剤師、林業、水産、警察官などといった多くのジャンルの過去問があることが強みです。畜産といった技術職の範囲も含まれています。
その他では、人事院に請求することで公務員試験の過去問を手に入れられます。
過去問対策はいつから始める?
さて、公務員試験の過去問対策はいつから始めるべきでしょうか。
近年では大学2年生から公務員試験の勉強を始める人がいますが、公務員試験合格者の大半は3年次から公務員試験の学習しています。
また、公務員試験合格者は過去問を受験前年度から3年分くらいは演習していると言われています。
人によって勉強するペースは変わってくるので、しっかりと自分で過去問を活用するタイミングを図りましょう。
高卒(初級)・大卒程度(上級)で必要な過去問対策は異なる?
公務員試験には、高卒程度の初級程度の問題と大学卒業程度の上級程度の問題があることを確認しましたね。それでは、高卒程度と大卒程度の問題で必要な過去問対策は異なるのでしょうか。
高卒程度の初級でも大卒程度の上級の問題でも、過去問対策において大きな差はありません。初級程度の教養知識をもとに上級程度の問題で応用するようなイメージです。上級程度だからといって、特別難関な問題が出題されるということはないので、そこまで不安にならないでください。
ただ、大卒程度の問題では、受験生を混乱させるための不必要な情報が含まれている場合がなくはないです。その問題に当たった際に、頭が真っ白にならないように、そのような問題があるということを本記事を通じて知っておきましょう。冷静に文章を理解するトレーニングも欠かさずにしましょう。
とにかく、高卒程度の公務員試験や大卒程度の公務員試験を受験しようが、基礎的かつ教養的な内容を網羅的に学習し、教養知識の定着と情報・知識の整理することが大事と言えます。
また、その教養科目における知識を自分の強みとして、差をつけて国家公務員試験合格を目指しましょう。
さて、これらを踏まえて、高卒程度の問題と大卒程度の問題において、過去問対策ポイントを詳しく見ていきましょう。
高卒(初級)程度の過去問対策ポイント
高卒程度の過去問対策として大事なことは、知識は前提として過去問を解くことを通して時間配分をどうするかです。1問にかける時間を間違えてしまうと試験時間が足りなくなってしまうことや、それによる焦りから本来の実力を発揮できない可能性が生まれてしまいます。
専門試験では大卒程度の問題と異なり、技術、農林土木と林業のみになります。やらなくてよい範囲まで学習しないようにちゃんと確認しておきましょう。
高卒程度の内容をスピード重視で学習したい人には、公務員試験スーパー勉強法という教材を使うのが良いでしょう。
大卒(上級)程度の過去問対策ポイント
大卒程度の過去問対策として大事なことは、高卒と比べると出題範囲が広いため、幅広い教養知識が求められます。
自分の得意あるいは不得意分野を明確にして、いかに効率良く知識を入れて、過去問でアウトプットすることと問題に慣れることができるかが大事です。
高卒程度と大卒程度の公務員試験過去問対策として共通して言えることは、いかに過去問を解いて、問題を分析したゆえ、問題の傾向を掴めているかどうかです。あとは、受験する前にしっかりと年齢制限を確認しておきましょうね。
あなたにとって効率の良い勉強方式・公務員試験までの用意

公務員試験に合格できるように効率の良い勉強方法を紹介します。
先ほど、過去問演習は重要と言いましたが、ベースとなる教養知識なしでは問題を解いたところで意味がありません。自分がどこの範囲を優先させるのかを決めて、基礎である教養知識から学習することをおすすめします。
公務員試験に合格するには最低でも800時間程度の勉強と言われています。自分に必要な勉強時間の程度を把握し、可能な範囲で教養知識の学習と過去問対策計画を立てることも大事でしょう。
最初からスケジュール通りに継続して学習するのは難しいと思うので、1日にみっちりと勉強している時間を把握するべきです。そうすれば、机に座っていても勉強できていない時間を知ることができます。そうすれば、改善点を見つけて学習プランを再確認できます。
1日に覚えられる量は限度があります。1日とても頑張って覚えても次の日も継続して学習しなければ意味がない。そうならないように、記憶科目で脳を消耗し、計算科目で気分転換することをおすすめします。これを繰り返し行い、習慣化されることでかなり効率よく学習する好循環を生み出せます。集中を妨げてしまうようなリラックスとは異なりますね。
また、勉強方法には独学と予備校に通う選択肢があります。
独学だと金銭的コストを抑えれれうメリットがある反面、情報収集や勉強・過去問対策サポート受けられないデメリットがあります。
予備校に関しては、カリキュラムに沿って学習できることから教養知識を身に付けやすく、詳しい過去問対策を相談できてライバルが身近にいて刺激的なメリットがある反面、金銭的なコストがかかり、忙し方にとっては通学が難しいデメリットがあります。
現環境によって選択肢は異なると思いますが、自分が最適と思う方法で教養を身に付け、過去問に取り組み、国家公務員試験準備をしましょう。
公務員試験対策は予備校や専門学校がおすすめ
これまで見てきて、国家公務員試験に合格するためには、かなり多くの準備が必要と分かりましたね。
公務員試験に臨むにあたり、独学では何から手を付けていいのか分からない方やどれくらいのペースでどれくらいの演習が必要かどうかなど学習しておくべき程度が分からない方がいらっしゃると思います。その程度がわからいままだと、思うように勉強が捗らず、学習や過去問対策など効率が悪くなってしまうことが問題となってしまいます。
そのような問題を抱えてしまいそうな方は、国家公務員試験に向けた予備校や専門学校に頼って公務員試験対策をすることをおすすめします。
では、国家公務員試験対策専門の予備校と専門学校のそれぞれの特徴などを詳しく見ていきましょう。
予備校
国家公務員試験の対策をしている予備校は多くあります。予備校は通学と通信で国家公務員試験の対策をするか選択することができます。どちらも講義でインプットした知識を、内容復習してから問題を解くアウトプットします。のちに、講義で学習した分野ごとに確認テストをしてから定期期に本番形式のまとめテストを行います。このようなスケジュールで本番の国家公務員試験に臨みます。
費用に関しましては、予備校通学だとおよそ50万円程度で、通信講座だと5~30万円程度です。
予備校通信による学習にすれば、時間や場所を問わず、自分のライフスタイルに合わせて学習することができます。
さらに、予備校にはターゲットとしている講義に特色がそれぞれあります。例を挙げると以下の通りです。
- 地方上級・国家一般職+専門職・裁判所カリキュラム
- 10カ月合格行政系公務員併願総合コース
- 地方上級・市役所教養合格コース
- 行政職実践
- 地方上級・国家一般職、スーパースペシャルコース
- 国家一般職・地方上級コース
対応するものが豊富なことが分かりますね。
専門学校
専門学校は、受講期間が1年~2年程度のものが一般的です。費用に関しては、コマ数と受講期間によって異なります。ただ、この公務員試験に向けた専門学校は誰しもが入学できるわけではありません。そこまで難しい問題ではありませんが、それに合格しないと入学できません。
専門学校は、長年にわたる公務員試験の過去問から出題傾向を分析すると同時に、最新の入試傾向にも注目した指導を行っていることが特徴です。
公務員試験に関する情報量が豊富なうえ、独学ではなかなか対策するのが問題となる面接や論文対策をしっかり受けることができます。専門学校では、プロの講師陣が揃っており、その方たちから直接指導を受けることができます。
同じ目標を掲げた生徒が身近にいることで、モチベーションの維持に繋がることがあるでしょう。
さらに、少人数クラスや講師など条件で選ぶことができます。無料のオープンキャンパスなどがあるので、学校の雰囲気などを知るためにも、それを活用していきましょう。
予備校や専門学校は、公務員試験を熟知しているため、カリキュラムに沿ってしっかり学習すれば公務員試験に合格する可能性は独学よりも高いです。
自分に適した予備校あるいは専門学校を調べ、そこで公務員試験の対策をすることをおすすめします。
まとめ

いかかでしたでしょうか。
公務員試験の内容、過去問対策と高卒と大卒で過去問対策の差異と効率の良い学習方法のほか、公務員試験対策としての予備校と専門学校について見てきました。
いかに教養知識を身に付け、それをベースに過去問を解くことが重要か分かったと思います。
また、いかに効率良く公務員試験対策をするには予備校や専門学校を活用すると良いことも知ることができましたね。
自分に適した学校選びや、スケジュール管理と学習スタイルを確立させて、公務員試験に合格できる学習をしていきましょう。
インターネットで調べると、無料で実力診断テストを受けることができます。pdfをダウンロードして1回だけでもやってみてはいかがでしょうか。
また、lec公務員アプリというものもあり、それでも学習することはできます。
書籍で学習するなら上述の通り、新スーパー過去問ゼミがおすすめです。
2022年の公務員試験の受付はもう始まっています。
教養知識をつけたうえで過去問をちゃんとした方法で活用し、公務員試験を合格したい方はトライしてみてはいかがでしょうか。