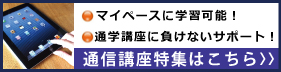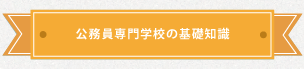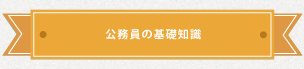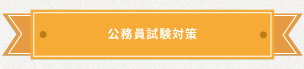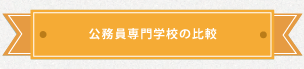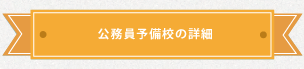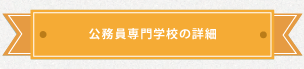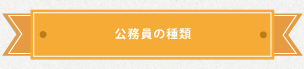業務規程・法律で制限!公務員の副業の現状

働き方改革が進み、「副業」に対する注目は年々高まりつつあります。公務員として働いている方の中にも、副業を検討している方もいるのではないでしょうか。
しかし、公務員は地方公務員・国家公務員に関わらず、民間企業とは違った制約があります。
そのため、世間的には広がりつつある副業も、なかなか身近なものになりにくい面があります。
とは言うものの、そういった現状を変えようと「公務員の副業解禁」が進んでいるのも事実です。
今回は、そんな公務員の副業について、規定・法律面に関する現在の状況や、今からできる副業について解説していきます。
公務員は副業が禁止?その理由とは
地方公務員や国家公務員は、副業による収入を得ることを法律によって制限されています。
地方公務員法第38条によると、地方公務員は任命者の許可を受けない限り、営利目的の活動に従事してはならないとされています。
国家公務員に関しても、国家公務員法第103条で営利目的の活動に従事してはいけないという旨が書かれており、このような法律があるために公務員の副業は難しいとされているのです。
このような法律が定めされているのは、公務員が業務を行う上での原則があるため。
具体的には、「公務員としての信用を失わないこと」「公務員としての業務に関する秘密が漏れないようにすること」「公務員としての業務に支障がでないようにすること」、この3つが公務員の原則です。
公務員は一般の企業とは違い、国家・国民のために業務に従事しています。そういった面を考えると、信頼・信用を落とさずに公務員としての働きを全うすることが何よりも求められ、副業などの営利目的の活動に厳しく制限がかけられているのでしょう。
罰則・処分を受ける可能性
公務員が黙って副業を行った場合、法律違反となり、罰則や処分を受けることがあります。
罰則、処分については下記の4つがあり、どの処分が下るかはその時の事例によって異なります。
- 戒告:処分の記録が人事記録に残されること。給与、出世面で影響がある。
- 減給:給与の金額を減らされること。
- 停職:一定期間、職務に従事できず、給与も支払われないこと。
- 免職:公務員としての職を失うこと。
実際にアルバイトやパートなどの副業・兼業がバレて処分を受けた事例もあります。
2017年に札幌市の職員が飲食店でアルバイトを行い、懲戒免職処分。
2013年に、大阪市の職員がパチンコ店のアルバイトを行い、停職処分。
事例によっては、最も重い免職処分を下されることも。
特に、収入を大きく増やす目的での副業は「営利目的の活動に従事してはならない」という公務員法に触れてしまう可能性が大きく、気軽に副業を行うことはリスクがあると言えます。
解禁されつつある公務員の副業
現状ではまだ自由に副業ができるとは言い難い公務員ですが、実は徐々に副業解禁の動きも出てきています。
たとえば、2018年には政府によって閣議決定された「未来投資戦略2018」の中で「国家公務員については、公益的活動等を行うための兼業に関して環境整備を進める」という旨の方針が発表されました。
地方公務員についても、2019年に「地方公務員の社会貢献活動に関する兼業について」という資料が発表され、地方公務員の副業を後押しする方針が示されています。
政府が主体となってこのような副業解禁の方針を示していることもあり、今後も公務員の副業解禁はより進んでいくと考えられています。
副業・兼業の推進に積極的な自治体もある
まだまだ複業の解禁が浸透していない公務員業界ですが、公務員の副業や兼業を積極的に推進している自治体もあります。
<兵庫県神戸市>
公務員の複業推進の先駆けとも言える自治体で、2017年4月に「地域貢献応援制度」を作り、公務員の副業を一部認めました。
地域貢献応援という名前の通り、地域のNPO法人や他団体の活動など地域に対する公益性が高い活動に関して、公務員が報酬を得て手伝いをすることが可能です。
複業として公務員が参加することで、高齢化による地域団体の人手不足の解消にも繋がっています。
<奈良県生駒市>
奈良県生駒市は、2017年10月に「地域貢献活動を行う職員の営利企業等の従事(副業)の促進について」という方針を発表し、市の職員の地域貢献活動に対する参加を促すための基準を定めました。
この基準によって、NPO活動や子どもへのスポーツ指導などの地域活動に公務員が報酬を受け取って参加できるようになっています。
2018年8月には基準が一部改正され、基準の対象となる職員や活動できる地域の範囲を大幅に広げて運用を開始。公務員がより複業をしやすい環境づくりを積極的に進めている自治体と言えます。
兼業・副業を始める際の注意点
公務員の副業解禁が今後も進んでいくと見られていますが、その中で注意したいのが、「どんな副業でも許されるわけではない」という点。
政府から発表されている地方公務員・国家公務員の方針では、公務員の副業・兼業として言及されているのは「公益的活動」「社会貢献活動」です。
つまり、収入のアップなどの個人的な営利目的ではなく、国や地域の人々にとって有益な活動を行うということが前提になった副業でなくてはいけません。
そのため、どんな副業でも認められるわけではないことは承知しておきましょう。
収入を増やしたい公務員におすすめの活動
先ほど説明したとおり、公務員の副業・兼業は徐々に解禁されつつありますが、全国的にはなかなか広がっていないのが現状です。
また、認められている活動も公益的活動や社会貢献活動に限られてしまうので、民間企業と比べて副業の自由度があまり無いという面もあります。
しかし、そんな状況の中でも、営利目的と判断されない範囲で行うことができる活動があります。
あくまで「営利目的ではない」という形になるため、副業と言えるほど大きな収入源になるわけではありませんが、今からできる収入源の確保の手段として参考にしてみてください。
不動産賃貸
公務員にもおすすめな副業として挙げられるのは、不動産の賃貸業です。
ビジネスとして不動産売却や大規模な不動産経営で大きな収入を得るのではなく、個人ができる範囲の不動産の家賃収入によって一定の収入を得るだけであれば営利目的とはみなされないことがあるため、公務員でも行うことができます。
ただし、下記の条件を満たす必要があるなど、制限がある点に注意が必要です。
- 管理会社に業務を全て委託すること
- 賃貸業による収入は年収500万円まで(これを超えると、許可が必要)
- 戸建ての賃貸不動産は5棟未満、マンションの場合には10室未満 など
また、自治体によっては賃貸収入の大きさに関わらず許可が必要な場合もあるため、事前に確認しましょう。
投資(株式・投資信託・FX)
株や投資信託、FXによる営利目的ではない投資は、公務員も行うことが可能です。
ただし、投資によって利益が出た場合には確定申告をする必要があるため、忘れないようにしましょう。確定申告を忘れた場合、無申告として罰則の対象となってしまいます。
投資の中でも、株式投資や投資信託は長期的な資産運用としても人気があり、気軽に始めることができるでしょう。
一方、FXに関しては為替の変動を常に気にする必要があるため、パソコンの前に張り付きでチェックしなければいけないこともあります。
そのため、公務員にとってはなかなか手を出しづらい投資方法です。為替変動によるリスクも大きく、投資に慣れていない人にはあまり向いていません。
安定した投資を行うのであれば、株や投資信託のほうがおすすめと言えます。
小規模農業
小規模な農地での農業は営利目的とみなされないため、公務員におすすめの副業です。
農家として継続した収入を得るというよりは、自分の家で食べる野菜や米をまかない、余った野菜を売ってちょっとしたお金を稼ぐといったイメージです。
どこまでが小規模農業といえるのかは、耕作面積が30a以下、または農産物の年間販売額が50万円以下が基準とされています。
これを超えると「販売農家」という区分になるため、許可が必要になることがあります。
広い土地を持っている人や、家業として大規模な農業を行っているなどの場合には、営利目的としてみなされてしまうことがあるため、よく確認しましょう。