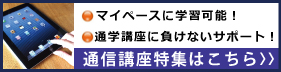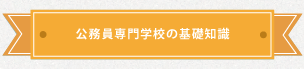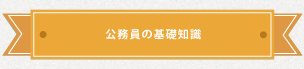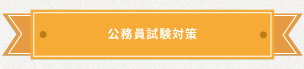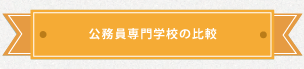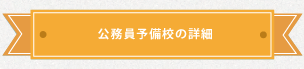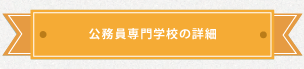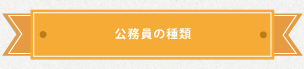公務員試験の二次試験では、人物試験(面接試験)が行われます。
近年、面接試験の重要性が増していることもあり、事前に万全な対策を講じておくことが合格への近道となります。
ここでは、公務員試験の面接を受けるうえでのポイントやよく聞かれる質問への答え方、公務員試験の面接に受かる人・落ちる人の特徴などについて詳しく解説していきます。
- 目次
公務員試験の面接を受けるうえで大切なポイント

公務員試験の面接を受けるにあたり、事前に十分な対策を講じておく必要があります。
公務員として求められる人材を理解したうえで、限られた時間内で自己アピールをできるかどうかがポイントになります。
公務員として求められる人物像を理解する
公務員試験の面接時間はひとりあたり20~30分程度のことが多いため、限られた時間内で面接官に自己アピールできるかどうかが重要です。
効果的にアピールするためには、「公務員として求められている人」はどのような人なのかを理解し、自分がそれに値する人材であると伝えることが大切です。
公務員という職業柄、地域貢献をしたい人や協調性のある人、堅実な人、温厚な人などが求められる傾向にありますが、さらに細かく、自分が希望する職種で求められている人物像を理解することから対策を始めると良いでしょう。
民間企業の就職試験とは異なる
民間企業でも就職試験で面接が行われていますが、公務員試験の面接とは性質が大きく異なります。
民間企業の面接は、一般的に人事部などで長年面接に携わってきた人が面接官を務めます。
いわば、採用におけるプロが入社希望者を面接し、「この人を採用すると自社にとってどれくらい有益なのか」を判断します。
一方、公務員は3年程度で部署が異動になることが多く、公務員試験の面接官も数年単位で変更されます。
プロによる面接が行われるわけではなく、面接経験の浅い担当者が行うことも。
そのような事情もあり、公務員試験の面接は「公務員としてふさわしくない人をふるいにかける」というスタイルになる傾向があります。
公務員試験に全落ちした場合に備え、民間企業への就活も同時にすすめている人は、公務員試験と民間企業の面接の違いをはっきりと区別し、それぞれ別個に対策を立てることをおすすめします。
質問により論理が矛盾しないように注意する
公務員試験の面接で特に注意したいのが、一つひとつの質問によって論理が矛盾しないようにすることです。
前に言ったことと後に言ったことで矛盾が起きていると、面接官に不信感を与えてしまいがち。
相手に不信感を与えてしまう人は、公務員には不適切と判断されてしまう可能性があります。
矛盾が起きないようにするために、エントリーシートや面接カード(質問カード)を熟考し、ほかの人に確認してもらうことがポイントです。
できればLECやTAC、大原などの公務員試験資格予備校の面接対策講座を受けられると安心です。
公務員試験を独学で受験する場合は、学校の先生などに確認してもらい対策を練ると良いでしょう。
頻出テーマは特に練習する
一般的に、公務員試験の面接で問われる質問はある程度決まっており、面接官にはあらかじめ質問リストが渡されています。
また、公務員試験の受験者が先に提出した面接シートを元に面接がすすめられることも多いので、その場で答えに窮するような質問をされることはほぼないといえます。
公務員試験の面接で聞かれる質問について、自分の回答をまとめたうえ繰り返し練習しておくと、面接対策はより万全なものになるでしょう。
なお、頻出の質問内容については次章で詳しく解説します。
公務員試験の面接でよく聞かれる質問

公務員試験の面接で聞かれる質問はだいたい決まっており、それらをスムーズに回答できるよう対策がとれると合格の可能性がアップするでしょう。
では、公務員試験の面接では具体的にどのような内容の質問がなされるのか、詳しく解説していきます。
公務員試験の頻出質問①:公務員を希望する理由は何ですか?
公務員試験の面接では、公務員を希望する理由を質問されることが多いです。
こういった質問の場合、「地域住民の役に立ちたい」、「地域の発展を後押ししたい」といった理由が思い浮かびがちですが、これではほかの受験生と差をつけることができません。
自分が希望する職種の仕事内容をしっかりと理解したうえで、自分には何ができるのかをアピールすることが大切です。
たとえば、学生時代に勉強したことや卒論で研究したこと、興味を持ったことを活かして、希望する職種でどのようなことをしたいのかを述べると良いでしょう。
また、民間企業と公務員には「利益の追求の有無」において違いがありますが、公務員を希望する理由として「民間企業は利益を追求するから公務員になりたい」といった回答は避けた方が良いでしょう。
というのも、公務員は住民からあずかった税金をもとに業務を行い、また税金から給料の支払いを受けているという事実があるからです。
民間企業の利益追求を否定するような内容の回答は控えるべきでしょう。
公務員試験の頻出質問②:なぜこの自治体(職種)を希望したのですか?
公務員試験の面接では、なぜその自治体(または職種)を希望したのか理由を問われることが多いです。
特に、都道府県庁や市役所などの地方公務員の場合は、生まれ育った自治体を希望することが多いですが、「自分が住んでいる地域だからです。」といった内容の理由では合格に近づくことはむずかしいです。
自治体の特徴を踏まえつつも、現在自治体ではどのような問題をかかえているのか、それに対しどのような政策を打ち出していてるのかなど細かいところまで理解したうえで、自分のできることや将来などを織り交ぜながら回答できると良いでしょう。
公務員試験の頻出質問③:自分が思う短所・長所を教えてください
公務員試験の面接では、自分の短所や長所について聞かれることも多いです。
自分で自己分析を行うことが苦手な人もいますが、客観的に自分を見つめて短所と長所を考えてみましょう。
そして、できれば裏付けされるエピソードや体験談・失敗談などを交えながら回答できると良いでしょう。
短所について回答する際は、長所の裏返しとなる内容にするのもポイントです。
たとえば、「行動が早い」という長所の反面「せっかち」という短所がある、といったイメージです。
そして、短所をどのようにカバーしているのかも伝えられると良い印象を与えられるでしょう。
公務員試験の頻出質問④:学生時代に頑張ったことはなんですか?
学生が公務員試験の面接を受ける際に必ずと言っていいほど聞かれる質問で、民間企業の面接でもよく聞かれる質問に「学生時代に頑張ったこと」があります。
学生にとっては自己アピールができる質問のひとつなので、事前にしっかり内容をまとめておきたいもの。
具体的には、勉強はもちろんのこと部活動や留学、ボランティア活動などがあるでしょう。
何をして、どのようなこと学び・失敗し、それを今後の仕事にどう活かしていくかといった内容でまとめます。
なお、公務員試験の社会人採用枠で行われる面接では、転職前の仕事でどのような業務に携わり、どのような実績を上げたのかなどをアピールできると良いでしょう。
公務員試験の頻出質問⑤:配属先が希望した以外の場所だったらどうしますか?
公務員試験の面接では、希望職種を聞かれた後に「もし希望していない職種に配属されたらどうしますか?」という内容の質問をされることがあります。
面接官は、受験者のやる気があるかどうかを推しはかっているため、「希望部署以外の場合は辞めます。」といった内容の回答をするのはNGです。
たとえ希望通りの職種や部署ではなくても、「配属先で一から勉強するつもりでがんばります。」という姿勢を期待しているのです。謙虚に努力し続ける姿勢が求められているといえます。
受かる人・落ちる人にはどんな特徴がある?

公務員試験の面接に受かる人と落ちる人にはどのような違いがあるのでしょうか。
公務員試験の面接に受かりやすい人の特徴がわかれば合格への道も近くなるといえます。
では、それぞれの特徴について解説していきます。
公務員試験の面接に受かる人の特徴
公務員試験の面接に受かる人には、次のような特徴があることが多いです。
- 公務員になってやりたいことが明確な人
- まじめで誠実な人
- 清潔感がありマナーが身についている人
公務員試験の面接では、公務員になった際にどのような仕事をしたいのか明確な考えを伝えることが大切です。
面接官は、それをもとに受験者のやる気や適性を判断しているのです。
また、公務員という性質上、まじめで誠実な人が求められる傾向があります。
着実に正確に職務をこなす能力がある人が受かりやすいといえます。
公務員は職種や部署にもよりますが、地域の人と接する機会が多いことがあります。
清潔感があり一般的なマナーを身につけている人が好まれるのはいうまでもないでしょう。
公務員試験の面接に落ちる人の特徴
一方、公務員試験の面接に落ちる人には次のような特徴があります。
- 自己アピールが弱い
- 信頼性に欠ける
- 志望動機がありきたりすぎる
公務員試験の面接で自己アピールが十分にできないと、面接官に自分がどのような人なのかを伝えることができず、「この人材が欲しい。」と判断してもらうことは難しくなります。
また、公務員はまじめで誠実な人が求められるため、信頼性に欠けると判断されてしまうと合格するのは非常に難しいでしょう。
面接中の言動や質問への回答などで信頼性に欠けることがないよう、日ごろからマナーに気を付ける必要があります。
さらに、公務員になりたい志望動機がありきたりすぎるとほかの受験生と差をつけることができずに合格に至らないケースがあります。
先にも触れましたが「地元だから受けた。」といった内容の回答はNGです。
公務員試験の面接に適した服装・マナー

公務員試験の面接では、服装やマナーにも気を配る必要があります。
一般的に、一次試験の筆記試験は服装の決まりがなく私服で受験する人がほとんどですが、二次試験の面接はスーツで受けるのがマナーです。
では、公務員試験の面接にはどのような服装やマナーに気を付ければよいのか、具体的に確認していきましょう。
公務員試験の面接にはスーツで臨む
公務員試験の面接はスーツを着用して臨みます。
新卒の人や20代の人はリクルートスーツを、それ以上の年齢の社会人は日ごろ着用しているスーツを選びましょう。
いずれの場合も、色は濃紺やグレーといった落ち着いた色のものを選びます。
男性の場合は、シャツは白のものを、ネクタイは派手過ぎないものを選びます。
靴は黒の革靴が無難でしょう。
カバンも同様に黒い革製のものがおすすめです。
当日の朝は、シャツにアイロンがかかっているか、靴は磨いてあるか、襟がずれていないかなどをチェックします。
全体的に、清潔感が保てるように意識しましょう。
女性の場合は、紺色やグレーといった落ち着いた色のスーツで、スカートでもパンツでもどちらでも良いです。
ブラウスは白やクリーム色などやわらかい印象のものがおすすめです。
靴はヒールの高すぎない黒いパンプスを。アクセサリーやネイルなどは派手なものは控えて最小限に抑えるのもポイントです。
髪型も清潔感を感じさせるようにすっきりとスタイリングすると良いでしょう。
公務員試験の面接ではマナーもチェックされる
公務員試験の面接では、服装だけでなくマナーもチェックされています。
たとえば、面接室に入る際や退出する際にノックをしているか、挨拶がしっかりできているかなどです。
マナーに不安な人はマナー本などでひと通り確認しておくと安心です。
当日は緊張していることが考えられるため、ひごろからマナーを意識しておくことも面接対策となります。
まとめ
公務員試験の面接を受ける際には、事前に十分に対策を練っておく必要があります。
公務員として求められている人物像を理解したうえで、より効果的な自己アピールができるかどうかがポイントになります。
ここで紹介した内容を参考にして、できうる限りの面接対策を講じておきましょう。