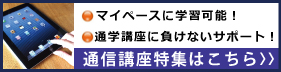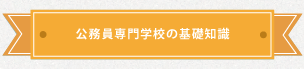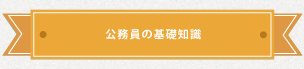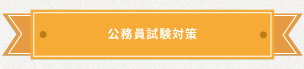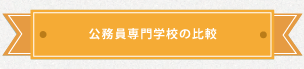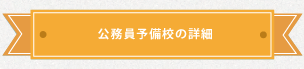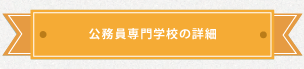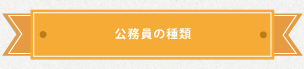公務員試験ってどれくらい難しいの?
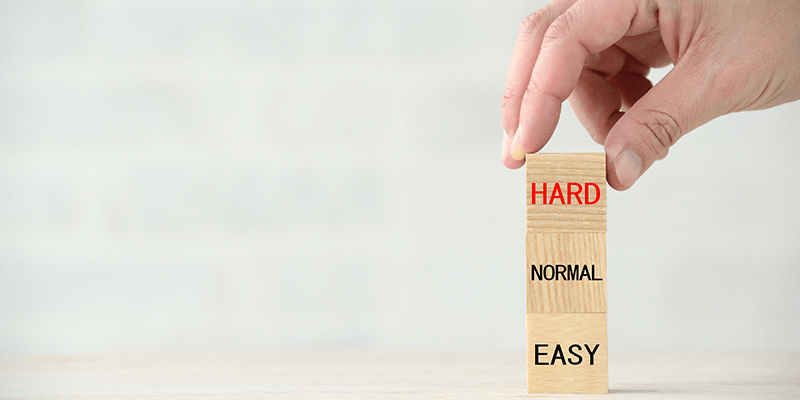
売り手市場と言われる就職市場においても未だ、根強い人気を誇る公務員。その公務員試験に関してお話しする際には必ず出てくるのが公務員試験の難易度はどれくらいなのかといったもの。
確かに公務員試験は色々な種類もあり、難易度もそれぞれ違います。
ただ難易度は競争率も関係するので、公務員試験の全体を把握し、ご自身が目指したい分野をはっきりさせる、そして難易度を考慮した上で公務員試験を受けるといったステップで進むことをおすすめします。
公務員試験を勉強中、またはこれから目指す人は試験難易度を確認して職種選びの参考にしてみて下さい。
公務員試験の難易度別で解説【SランクからDランクまで】

先ほどお伝えしたように公務員試験と一言で言っても様々な種類があり、その種類分だけ難易度にも差があります。
その年の競争倍率や試験傾向によっても異なってきますが、公務員を目指す上での参考になればと思います。
ただし、 難易度は低くても競争率の高い試験は合格は難しくなります。難易度だけに捉われず、自分の得意分野、夢、競争倍率などを含めて総合的に判断して公務員を目指してください。
また、同じ都庁I類であっても専門性の高い土木や福祉は、人気の高い事務などに比べて倍率が低く難易度も下がるケースもあるため、過去の試験結果などはしっかり確認しておくことが重要です。
今回はSランクからABCDと分けて公務員試験の難易度について解説していきます。まずは最難関Sランクから。
難易度Sクラスも!最難関の公務員試験はこれ
| 試験の種類 | 難易度 |
|---|---|
| S+ | 国家公務員(国家総合職)財務省、経済産業省、総務省、警察庁 |
| S | 国家公務員(国家総合職)外務省、文部科学省、防衛省、内閣府、金融庁、会計検査院、厚生労働省、衆議院・参議院総合職 |
| S- | 国立国会図書館総合職、裁判所事務官総合職 |
どの試験も難易度が高いうえに競争倍率も高いので、非常に高度な知識と面接での対応力が要求されてきます。
また、国家総合職は 東大、京大、早慶などの一流大学の受験生との競争試験となり、試験合格後の採用まで考えると省庁によっては学歴も必要となります。
ちなみに国家総合職2018年度の合格者数は1位が東京大学(329名)で2位は京都大学(151名)となっており、その中でも1位と2位だけでも大きく差が開いていることから圧倒的に東大卒が多いことが分かります。
私立に関しては、早稲田大学が1位(全体3位)で111名、続いて慶応義塾大学が2位(全体で4位)の82名と、日本の名門大学が上位を占める結果に。
このようなことから判断すると難易度Sランクの公務員試験は独学で合格を勝ち取るのは 非常に困難です。公務員専門学校や資格の予備校の公務員講座を受講して対策を取る必要があります。
そういう意味でも数々の公務員試験合格の実績豊富でノウハウを有する公務員専門学校などを選ぶことが高難易度の試験合格には非常に大事になってきます。
まだまだ非常に難易度が高いAランクの公務員試験
| 難易度 | 試験の種類 |
|---|---|
| A+ | 下位国家総合職(国土交通省、環境省、農林水産省、法務省など)、制作担当秘書、防衛大学 |
| A | 上位都道府県庁上級(東京都庁・大阪府庁・愛知県庁、千葉県庁、神奈川県庁、埼玉県庁、福岡県庁、北海道同庁) |
| A- | 上位政令都市・特別区上級(神戸市、札幌市、名古屋市、東京23区など)、気象大学、衆議院・参議院一般職(大卒)、国立国会図書館一般職(大卒)、裁判所事務官一般職(大卒)、外務省専門職 |
難易度Sに比べるとAランクになったからと言って、難易度は非常に高いです。これらAランクの公務員になるためにはかなりのレベルを必要とされるでしょう。
大卒以上を求められる公務員試験の中でもさらに成績が優秀な受験生が多く目指している職種となります。また、 専門性が高い職種に関しては採用人数が少ないのも相まって非常に競争率が高く合格するのが困難となっています。
都庁や政令都市などの県庁・市役所は年収が高い上に都市部に位置するため人気があります。
このようにAランクに位置する公務員試験はレベルの高さももちろん、人気による競争率の高さから合格するのは 非常にハードルが高いと言えるでしょう。Aランクの公務員試験を受験されることを考えている方は、間違いなく合格実績の高い公務員専門学校で合格対策講座を受講することをおすすめします。
なお、高い語学力を求められることで有名な外務省専門職を目指すのであれば、 Wセミナーが特におすすめです。
2018年度の試験では合格者49名中43名がWセミナー生であり、合格者占有率は 837.8%と難易度Aにもかかわらず、ほぼ独占する高い実績を誇っています。
ここからやっと独学での合格が見えてくる?!公務員試験難易度Bランク
| 難易度 | 試験の種類 |
|---|---|
| B | 地方上級下位【県庁・政令都市】、中核市、国家一般職、自衛隊幹部候補生、法務省専門職員、労働基準監督官、食品衛生監視員 |
難易度Bランクは公務員試験の中でも 一発合格が現実的に見えてくるレベルになります。
中堅レベルの私大など多くの大学生が対策をきちんとすれば合格を引き寄せることが可能に。
但し、あくまで公務員試験の中では標準レベルなだけで、 他の資格試験などに比べると難易度は高いので油断はできません。
多くの方がこのCランクに位置付けした公務員試験を受けるので対策をしてくれる公務員専門学校も豊富揃っています。
比較検討しながら自分に合った学校をみつけやすいでしょう。その豊富にあるノウハウをどう自分のものにするのかがカギと言えそう。
逆に独学でのCランクに位置付けられた公務員試験受験は、よほど自信がある方でなければおすすめしません。
無理に独学で勉強して試験に何度も落ちてしまうのであればお金や時間がもったいないですから。
ここからやっと身近に感じる公務員職に。難易度Cランク
| 難易度 | 試験の種類 |
|---|---|
| C+ | 教員採用試験、市役所【大卒】、地方中級【政令都市・都道府県庁】、財務専門官、国税専門官、皇宮護衛官【大卒】、海上保安官【大卒】、航空管制官 |
| C | 裁判所事務官【高卒】、衆議院・参議院職員【高卒事務局・衛視】、国立国会図書館【高卒】、国家一般職【高卒上位省庁】、海上保安大学校 |
難易度Cランクはきちんと勉強をすれば合格が可能なレベル。
特に、教員採用試験や市役所は 一般的な大卒くらいの学力があれば合格可能。
特に教員は昨今の団塊世代の大量退職により、多くの自治体で採用者数が増加しているおすすめの職種です。
ただし、どの 職種も競争率は非常に高く、10倍を超えることも珍しくないのでしっかりとした対策や準備を行なうことが重要です。
公務員試験のレベルよりも競争率の高さがハードルとなるので、きちんと自分のペースで勉強や対策ができないのであれば公務員専門学校に通い環境を整えるのも大事です。
難易度Dランク
| 難易度 | 試験の種類 |
|---|---|
| D+ | 地方初級【県庁・政令都市】、国家一般職【高卒下位省庁】、入国警備官、皇宮護衛官【高卒】、税務職員、海上保安学校、大卒警察官、大卒消防士 |
| D | 警察事務【高卒・短大】、学校事務【高卒・短大】、市役所【高卒】、短大卒の警察官・消防士 |
| D- | 高卒警察官・消防士、自衛隊 |
難易度Dランクは公務員試験の中でも比較的 易しく公務員になりたい方にはおすすめの職種です。
D-に評価した自衛官は2等陸・海・空士のことを指します。自衛官は人材が足りておらず、採用予定数も多いため採用されやすい特徴があります。
また、年齢上限を26歳から32歳と大幅に引き上げる方針が決定されているので、今後はより多くの人が受験できるようになります。
さらに、少子化による人材不足解消や士気向上を目的として、手当拡充や勤務環境の改善などの待遇改善が調整されているため、より働きやすい環境が期待されています。
しかし、自衛官は身体検査、体力検査があるので体力に自信の無い人にとっては難易度は高くなります。
刑務官は、 犯罪者の更生や死刑執行などを担当する職務のうえ、公務員の中では離職率の高い職種となっています。
ただ難易度で選ぶのではなく、しっかりとした動機が無いと継続して勤務することが困難な職種かもしれません。あらかじめ、職務内容などしっかりと確認しておくようにしておきましょう。
刑務官も自衛官同様体力検査があるので、体力に自信のない人は難易度が自ずと高くなります。
公務員試験の種類別競争倍率ランキング

大卒・院卒程度の国家試験倍率ランキング
| 順位 | 試験の種類 | 申込者数 | 第一次試験合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 皇宮護衛官(大卒) | 1,476 | 245 | 72 | 20.5倍 |
| 2位 | 国家総合職(院卒:教養区分) | 2,928 | 265 | 145 | 20.2倍 |
| 3位 | 国家総合職(大卒) | 17,428 | 2,354 | 1,158 | 15.1倍 |
| 4位 | 食品衛生監視員 | 496 | 98 | 62 | 8.0倍 |
| 5位 | 航空管制官 | 1,015 | 295 | 133 | 7.6倍 |
| 6位 | 財務専門官 | 3,529 | 869 | 526 | 6.7倍 |
| 7位 | 労働基準監督官 | 4,045 | 1,588 | 612 | 6.6倍 |
| 8位 | 法務省専門職員(人間科学) | 2,366 | 794 | 475 | 5.0倍 |
| 9位 | 国税専門官 | 15,884 | 6,075 | 3,479 | 4.6倍 |
| 10位 | 国家一般職(大卒) | 33,582 | 11,004 | 7,782 | 4.3倍 |
| 11位 | 国家総合職(院卒) | 2,181 | 1,137 | 639 | 3.4倍 |
| 12位 | 国家総合職(院卒:法務区分) | 22 | 12 | 11 | 2.0倍 |
高卒程度の国家試験倍率ランキング
| 順位 | 試験の種類 | 申込者数 | 第一次試験合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 国家一般職(社会人経験) | 402 | 43 | 16 | 25.1倍 |
| 2位 | 皇宮護衛官(高卒) | 555 | 135 | 23 | 24.1倍 |
| 3位 | 気象大学校学生 | 418 | 46 | 32 | 13.1倍 |
| 4位 | 入国警備官 | 2,072 | 275 | 185 | 11.2倍 |
| 5位 | 航空保安大学校学生 | 663 | 185 | 106 | 6.3倍 |
| 6位 | 海上保安大学校学生 | 504 | 150 | 81 | 6.2倍 |
| 6位 | 海上保安学校学生 | 3,650 | 1,220 | 592 | 6.2倍 |
| 8位 | 海上保安学校学生(特別) | 5,970 | 2,731 | 1,028 | 5.8倍 |
| 9位 | 税務職員 | 8,011 | 2,630 | 1,496 | 5.4倍 |
| 10位 | 刑務官 | 5,027 | 2,016 | 1,009 | 5.0倍 |
| 11位 | 国家一般職(高卒) | 14,455 | 4,585 | 3,289 | 4.4倍 |
ここでは、平成31年に人事院によって公表された平成30年度の国家公務員試験採用試験実施状況をもとに各公務員試験の競争倍率を算定しランキング化しています。
倍率と難易度は完全に比例していませんが、やはりランキングの上位を見てみると大卒・院卒および高卒かどうかに関係なく、募集人数の少ない皇宮護衛官や国家総合職(院卒:教養区分)並びに国家一般職(社会人経験)などの公務員試験合格の倍率は非常に高くなっていることがわかります。
また国家総合職(大卒)は、キャリア官僚の道が開かれた華やかな職業であり、募集人員もある程度確保されているので、該当公務員試験を受験する人が多いです。しかし難易度が高くても上位国立大学や早慶といった優秀な学生が集まるので難易度もさらに高まっているようです。
一方、国家一般職(大卒)は、中堅大学でも積極的に公務員ん試験を受験するとのですが、合格者数も多いので国家総合職と比較すれば倍率は低く留まっています。
これらの公務員試験合格の難易度はそこまで高くはないものの、もしも確度の高い公務員試験合格を目指すのであれば、申込者数が少なく穴場となりやすい公務員の職種もあるので、チェックしておくと良いでしょう。
難易度の高い試験ほど公務員専門学校がおすすめ
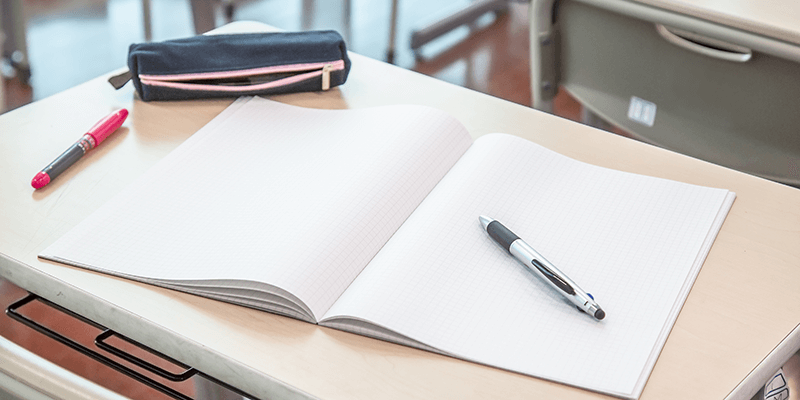
これらを踏まえた上で合格の可能性を高めるために独学も良いですが、公務員専門学校や予備校の対策コースを受講することをおすすめします。
何度も繰り返しになりますが、確実な対策が公務員試験合格のカギです。
たまに学費や授業料を節約するために独学で勉強する人もいますが、公務員試験は年齢制限があるので、確実に合格が目指せる公務員専門学校で学ぶことが進路で路頭に迷うリスク防止につながります。
難易度の低い職種でも公務員専門学校や予備校で対策するようにしましょう。
公務員試験の合格実績が違う
難易度の高い公務員試験ですが、公務員専門学校はやはりノウハウや情報量が豊富なので合格者数が非常に多いです。
公務員専門学校では大原の評判が良く、合格実績はトップクラス。
また、大原が地元にない人も、ビジネス専門学校などが公務員コースを開講していることが多いです。
合格実績豊富な公務員専門学校に通えば、自分も先輩たちの後に続いて合格できる可能性は高くなるので、相性の問題もありますが、まずは合格実績から公務員専門学校を探してみるのも1つの方法です。
特に高難易度の試験合格を目指す場合は、公務員専門学校の合格実績は大きく影響してきます。
法律など難しい内容も理解が進む
公務員試験では法律系の問題などは専門用語が多かったり、独特な言い回しがあったりで教材を読んだだけでは理解できないことも多いですよね。
そんな場合も、公務員専門学校の授業ではベテラン講師が分かりやすく丁寧に説明してくれるので理解も進みます。
不明点があっても、その場ですぐに質問できるので、独学のように理解できないまま放置してしまうリスクもありません。
他にも、経済や行政と言った専門科目も効率良く対策できるのが公務員専門学校の強みです。
学費・就職支援制度も充実
公務員専門学校を学費面で諦めている人は、まずは奨学金制度などを確認してみましょう。
中には学費が免除となる特待制度を設けている公務員専門学校もあります。
もちろん、特待制度は定員が限られており、一般入試よりも難易度は上がってしまいますが、挑戦する価値は大いにあります。
また、公務員専門学校では試験対策をするだけでなく、ビジネスマナーやパソコンスキルを習得する授業を用意していることも多いので、例え公務員試験に不合格でも一般企業への就職の選択肢もあります。
公務員専門学校によって一般企業への就職をサポートしているところもあるので、難易度が高い公務員試験のリスクヘッジとして検討してみるのもいいでしょう。
公務員専門学校の選び方

難易度の高い公務員試験を合格するには公務員専門学校への入学を強くおすすめしますが、現在のバックグラウンドによっておすすめの学習環境は大きく変わってきます。
そこで、大学生・社会人と高校生におすすめの学習環境を紹介していきます。
大学生や社会人は予備校の対策講座がおすすめ
大学生や社会人は時間の融通が難しいので全日制タイプの公務員専門学校はに通うことは難しいです。
この場合、公務員専門学校の夜間や資格予備校で開講している公務員講座の受講をおすすめします。
大学生や社会人でも効率よく勉強できるよう、授業の振替制度などが充実しているのが特徴です。
大卒程度の公務員試験では多くの人が利用して合格しているので、ダブルスクールも十分可能だと言えるでしょう。
高校生は公務員専門学校への入学がおすすめ
高校生の場合は、卒業後の進路として公務員専門学校へ入学することをおすすめします。
大学生や社会人が利用する公務員講座も受講できますが、やはり専門課程のほうがサポートが充実していて、ドロップ率も低いです。
したがって、合格率が高く、難易度の高い公務員試験の合格も夢ではなくなります。
また、公務員専門学校へ入学すれば卒業時に専門士としての学位が授与されるので、学歴としても記述できるのが魅力です。
説明会やオープンキャンパスに参加しよう
公務員専門学校や資格予備校で勉強する際は、必ず入学前にオープンキャンパスや体験授業に参加して自分との相性を見極めましょう。
公務員専門学校の学費は決して安くはありません。
また、難易度の高い試験に合格するためには、いかに相性の良い環境で効率よく勉強できるかが影響してきます。
公式サイトや資料だけでなく、実際に足を運んで自分の目でリアルな状況を確認してから入学の可否を決定しましょう。