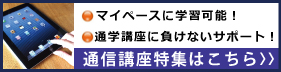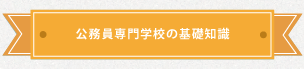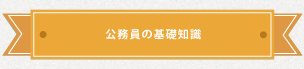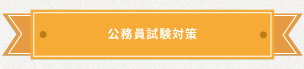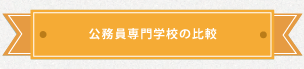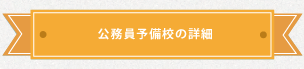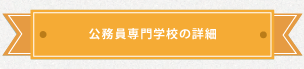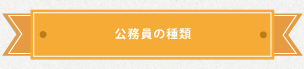国家公務員も地方公務員も人気があり、どちらの採用試験も難関として知られています。
特に東京や大阪、福岡などの大都市圏の地方公務員試験は競争率が高く、公務員浪人を余儀なくされる人も少なくありません。
中には3浪、4浪というケースも。
それを避けて1年合格を勝ち取るためには、公務員試験対策に特化した「公務員専門学校」で勉強することが一番です。
ここでは公務員専門学校の入試システムや試験の内容について紹介していきます。
公務員専門学校の入学試験

公務員専門学校は、公務員採用試験に合格するために必要な知識やテクニックを習得するところです。
修業年限は1年制と2年制があり、夜間部を設けている学校もあります。
修業年限が2年以上で、文部科学大臣や都道府県知事から認可された公務員専門学校(正式名称は専修学校)を受講するには、入学試験を受けて合格する必要があります。
ちなみに、修業年限が2年以上の教育過程を修了すると「専門士」の称号が付与されます。
専門士は短期大学卒業と同等の学歴とみなされるため、4年制大学の2年次または3年次に編入することが可能となります。このような点が各種学校や予備校と大きく異なるところです。
公務員専門学校の入学試験には、大学と同様に一般選抜、学校推薦型選抜(旧推薦入試)、総合型選抜(旧AO入試)の3種類があります。
学校推薦型は、専門学校側から指定された高校の生徒向けの試験で、高校長の推薦状が必要です。
総合型選抜は、専門学校側が求める学生像(アドミッション・ポリシー)とマッチングするかが問われる試験です。
どちらも専願が原則で、大学やほかの公務員専門学校と併願することはできません。
ここでは、推薦状が不要で併願も可能な一般選抜について説明します。
一般選抜でも重視されるのは志望理由書

一般選抜の試験内容は公務員専門学校によって異なります。
例えば、全国展開している大原学園の公務員専門学校では書類審査だけです。
書類に不備があったり、高校時代に欠席が多かったりした場合に面接が行われることも。
九州の福岡に本部を置く麻生(aso)公務員専門学校では、書類審査、志望理由シート審査、面接を実施しています。
応募者が多いときは学科試験(基礎学力調査)を課すところもありますが、いずれにしても公務員専門学校の入学試験で重視されるのは「志望理由・動機」です。
次項で審査に通りやすい志望理由書のポイントをまとめてみましょう。
合格につながる志望理由の書き方【4つのポイント】
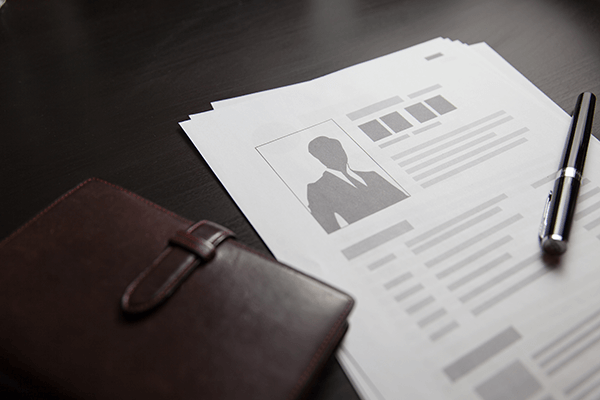
志望理由書は「エントリーシート」「自己推選書」とも呼ばれるもので、公務員専門学校によって文字数が指定されています。
200字、400字、800字、1200字などさまざまですから志望校の募集要項でよく確認してください。
志望理由・動機は、なぜその公務員専門学校に入りたいのかを書けばよいのですが、「安定した職業の公務員になりたいから」とか「親に勧められて」、「大学より公務員専門学校が入りやすくて学費も大学より安いから」といった書き方はNG。
学校側が志望理由書で見るのは主に「熱意」「人柄」「可能性」「文章力」です。それらをしっかり伝えるために下記の4点を押さえておきましょう。
ポイント1.その公務員専門学校で学ぶ動機・目的を明確にする
志望理由は単に公務員になりたいというだけでなく、国家公務員なら中央省庁で働く総合職を目指したいとか、地方公務員なら〇〇県の行政職に就きたいというように、就職を希望する職種・分野をできるだけ具体的に書きます。
そのうえで「公務員試験を熟知した先生方が生徒一人ひとりを手厚くサポートし、必要に応じて個人授業も行うという、先生と生徒の距離が近い学校と知り、ぜひ貴校に入学したいと思いました。」のように、その公務員専門学校に関する情報を盛り込んで熱意をアピールするといいでしょう。
また、「社会(地域)に貢献する仕事はどんな職業よりも価値があると思い、地方公務員を志しました。」といった動機をひと言加えるだけで志望理由書に深みが出てきます。
ポイント2. ネット上の志望理由書の例文や書き方を参考にする
志望理由書を作成するのは初めてで何を書けばいいのかわからない、という人は受験関連サイトに掲載されている記事を参考にすることをおすすめします。
志望理由書の成功する例文と失敗する例文が提示されているので、書き方のコツをつかむことができます。
もちろん志望理由書の成功例文を丸写しするのは禁物ですが、その公務員専門学校を選んだ理由・動機を伝えるのにふさわしい例文を基にして、自分らしい志望理由書を作成しましょう。
ポイント3.日本語の誤り・漢字間違いに気を付けること
志望理由・動機で自分をうまくアピールできても、誤字脱字や敬語の誤りなどがあっては高評価を得ることができません。
公務員の仕事でも文書や数字を扱う行政職は早さよりも正確さが求められますから、その職を目指す人は特に要注意です。
もし誤りに気づいたら、修正液を使って書き直したりせず、新しい用紙で作成し直すのがビジネスマナーです。
志望理由書は大半が手書きですが、書式をダウンロードしてパソコンで入力する場合もあります。
その際によくありがちなのが文字の変換ミス。たとえば、「~合格者を輩出している貴校で~」と書くところを「~合格者を排出している貴校で~」と書いてそのまま提出するケースがありますが、これでは真剣さに欠けると減点されてしまいます。
ポイント4. 先生などにお願いして志望理由書を添削をしてもらう
志望理由書を書き上げたら推敲して、誤字や不自然な表現を訂正します。しかし、推敲には限界があります。
自分の中では志望理由・動機がよくまとまっていて問題ないと思えても、読み手によって志望の理由・動機が意味不明ということがあり得るからです。
誰が読んでも志望の理由・動機がわかるように書くことが重要ですから、必ず第三者に志望理由書を添削してもらいましょう。
学校や塾の先生、家族などにお願いして冷静な目で読んでもらい、指摘されたところは素直に書き直します。
【まとめ】公務員専門学校もオープンキャンパスに参加してから決めよう
公務員専門学校に入るための試験は大学と違って難しいものではありません。
受験生の最終目的は本試験(公務員採用試験)に合格することですから、本試験の合格率が高い公務員専門学校を選ぶことが重要になってきます。
公務員専門学校の広告では「合格率98%」などと謳っているところが多く見受けられますが、中には誇大広告が疑われる学校もあります。
入学してから後悔することのないよう、オープンキャンパスに参加して講師やスタッフに質問したりして、信頼できると思える公務員専門学校を選ぶようにしましょう。