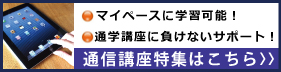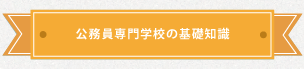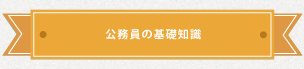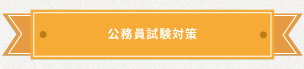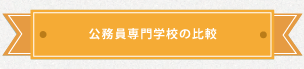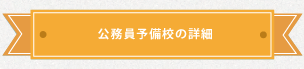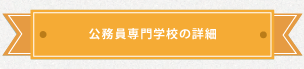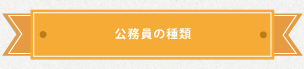公務員試験は面接が必須!人物試験の概要や質問内容、対策方法を解説

公務員試験では、1次試験を通過した後に2次試験で面接試験が行われます。面接試験には個別面接や集団面接、集団討論といった方法があり、それぞれ対策が異なります。
事前に質問される内容や面接の流れなどを知っておくと、落ち着いて面接試験に臨むことができるでしょう。
この記事では、公務員試験における面接試験の重要性や個別面接や集団面接、集団討論の内容や対策などについて詳しく解説していきます。
- 目次
公務員試験における面接試験の重要性
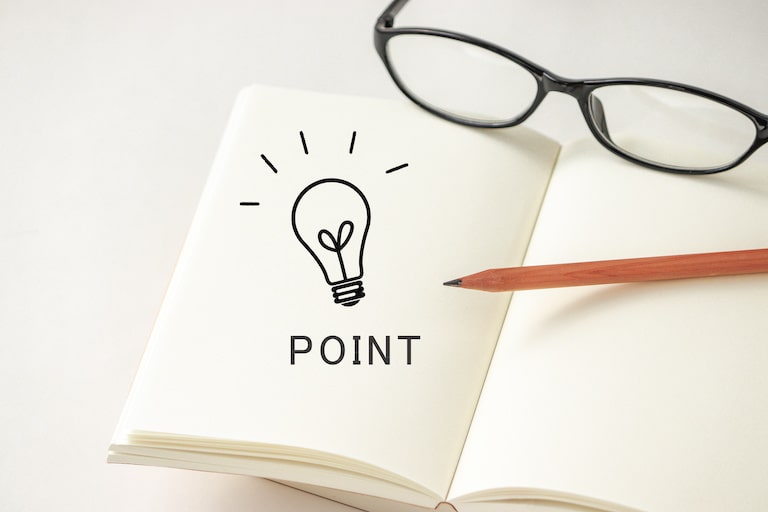
公務員試験の面接(面談)試験は、主に筆記試験が行われる1次試験を通過した人が受けられる試験です。
中には、1次試験に面接試験を実施するところもありますが、多くは筆記試験に受かる人のみが受けます。
近年、公務員試験全体における面接試験の重要性が増している傾向にあり、知識だけでなく受験者の考え方や表現力などが試される「人物試験」となっています。
では、面接試験が公務員試験においてどのくらいのウェイトを占めているのか、国家公務員試験や一部の地方公務員試験の配点比率を見ていきましょう。
国家公務員試験の面接の配点比率
国家公務員試験総合職(大卒程度)の配点比率は以下の通りです。
| 試験種目 | 配点比率 |
|---|---|
| 基礎能力試験 | 2/15 |
| 専門試験(選択式) | 3/15 |
| 専門試験(記述式) | 5/15 |
| 政策論文試験 | 2/15 |
| 人物試験 (面接試験) | 3/15 |
国家公務員試験総合職(大卒程度)で最も配点比率の高い試験種目は記述式の専門試験ですが、面接試験は選択式の専門試験とともにその次に多い試験種目となっています。
3/15であることから、全体の20%を占めていることになります。
続いて、国家公務員試験一般職(大卒程度)の配点比率を見ていきましょう。
| 試験種目 | 行政区分 | 建築区分 | 行政・建築遺体の区分 |
|---|---|---|---|
| 基礎能力試験 | 2/9 | 2/9 | 2/9 |
| 専門試験(選択式) | 4/9 | 2.5/9 | 4/9 |
| 一般論文試験 | 1/9 | - | - |
| 専門試験(記述式) | - | 2.5/9 | 1/9 |
| 人物試験 (面接試験) | 2/9 | 2/9 | 2/9 |
国家公務員試験一般職(大卒程度)では、行政区分・建築区分・それ以外の区分のすべての区分において面接試験は2/9となっており、全体の2割強を占めていることがわかります。
地方公務員試験の面接の配点比率
次に、地方公務員試験(大卒程度)の試験種目ごとの配点比率をいくつか例にとって見ていきましょう。
| 試験種目 | 埼玉県 | 神奈川県 | 大阪府 | 福岡県(行政) |
|---|---|---|---|---|
| 1次試験(教養) | 100点 | 100点 | 14% | 50点 |
| 1次試験(専門) | 100点 | 100点 | 28% | 50点 |
| 2次試験(論文) | 100点 | 50点 | - | 20点 |
| 2次試験 (人物試験・面接試験) |
300点 | 第1回面接50点、 第2回面接250点 |
57% | 100点 |
| 備考 | 令和3年度 | 令和3年度 | 令和元年度 | 令和4年度 |
自治体によって試験種目の配点比率が異なりますが、地方公務員試験の約半分は面接試験の配点が占めている自治体が多いことがわかります。
このように、国家・地方ともに公務員試験において面接試験が占めるウェイトが大きくなっていることから、面接試験が合格のカギをにぎるといっても過言ではないでしょう。
民間の面接試験とは異なること
面接試験は、公務員試験だけでなく民間企業の採用試験でも行われますが、公務員試験と民間の採用試験とでは面接試験の際に審査されるポイントが異なります。
一般的に、民間企業の採用試験では人事部といった従業員の採用や異動などを担当としている部署が行います。
人事部にはこれまで採用に携わってきた採用のプロ社員がおり、入社希望者の面接試験にあたります。
「企業の事業発展に貢献してもらえそうな良い人材を採用する」という観点をもとに面接を行います。
一方、公務員試験はやはり人事部の採用担当者が面接試験を行いますが、公務員はひとつの部署に長年とどまるということはほとんどなく数年単位で異動します。
そのため、採用担当のプロが面接試験にあたるというわけではないことが多いです。
面接試験の際には、民間企業のように良い人材を採用するということよりも「公務員として不適切な人を除外する」という観点をもとに面接が行われます。
というのも、公務員の仕事はミスをすると世間からの批判を受けやすく信用にかかわるので、面接でもミスをおかさないことが受かるためのポイントになります。
公務員試験の面接は3タイプある

公務員試験の面接試験は、大きく分けて「個別面接」、「集団面接」、「集団討論」の3つのタイプがあります。それぞれどのように面接が行われるのか確認していきましょう。
公務員試験の面接①:個別面接
受験者1人に対して4~5人程度の複数人の面接官で実施される面接試験です。
ただし、地方公務員試験によっては最適な人材を見つけるために各部署の採用担当者が出席し、総勢10人以上の面接官になるケースもあります。
また、個人面接は1回のみの公務員試験も多いですが、中には複数回行われるところもあります。
公務員試験の面接時間は、一般的に1回あたり15~30分程度で行われ、事前に渡されたエントリーシートや面接カードに沿って質問されることが多いです。
なお、エントリーシートや面接カードについては後ほど詳しく解説します。
公務員試験の面接②:集団面接
公務員試験の集団面接は、その名の通り複数の受験者を一度に面接する方法で、複数の受験者に対し複数の面接官が質問していきます。
質問に回答する方法は、指名制や挙手制、順番などさまざまです。
挙手制の場合は、自分が答えようとしたことがほかの受験生に言われてしまわないように、考えがまとまったらすぐに挙手するなどの対策が必要でしょう。
また、ほかの受験生の回答を聞くと緊張したり焦ったりしてしまうので、自分の答えをまとめることに集中できるよう対策をとっておくと良いでしょう。
公務員試験の面接③:集団討論
公務員試験の集団討論形式で行われる面接試験は、1グループ5~10人程度に分かれて、与えられた課題に対して討論し制限時間内に意見をまとめる形式で行われます。
面接官は、グループ討論の様子から受験者の考え方や協調性、コミュニケーション能力、社会性、時間配分能力などをチェックします。
また、公務員試験によっては、討論結果をプレゼンすることまで求められることもあります。
面接カードやエントリーシートの内容

公務員試験では、1次試験合格後に面接カードやエントリーシートが渡されます(ダウンロードするケースもあります)。
面接カードにはどのような内容を記入するのか、国家公務員試験一般職の面接シートを例に紹介します。
- 氏名、生年月日
- 住所、電話番号
- 学歴、職歴
- 志望官庁
- 趣味、クラブ活動
- 身体状況、長所・短所
- 資格
- 学生時代に力をいれたこと(学業、学業以外)
- 自己PR
- 志望理由
- 採用後にやってみたい業務 など
面接カードやエントリーシートは、国家公務員試験では事前に記入し面接試験時に持参することが多いです。
しかし、地方公務員試験では1次試験当日に提出するケースや願書提出時に提出するケース、面接日までに郵送するケースなどもありますので自治体の指示に従って準備してください。
個別質問対策

公務員試験の個別面接ではどのような質問をされるのでしょうか。
民間企業の面接とは審査ポイントが異なるうえ、面接試験は公務員試験の中で大きな配点割合を占めるので、事前に質問内容を把握し対策を練っておきたいものです。
では、公務員試験の面接で質問される頻出事項について見ていきましょう。
質問事項①:なぜ公務員試験を受験したのですか?
なぜ公務員になろうとしたのか、その動機を質問されることは多いです。「住民や地元の力になりたい」といった答えはありきたりなのでできれば避けたいところ。
「こういった仕事がしたい」など民間では対応しきれない事業などを具体的に考えて答えることがポイントです。
また、なぜその自治体の公務員試験を受けたのか、ほかの自治体ではなぜだめなのかも質問されることがありますので、納得できる回答ができるよう対策をとっておきましょう。
質問事項②:ほかに何を(どこを)受けていますか?
公務員試験は併願することが可能なので、ほかにどこを受けているのかを質問されることがあります。
公務員試験の併願のほかにも、民間企業を併願しているケースもあるでしょう。
併願していると合否に影響があるのではないかと心配になりますが、後で矛盾点が出ないように正直に回答するのもひとつの方法です。
質問事項③:今まで一番苦労したことはなんですか?
一般的に、民間企業ではこれまでの実績や経験などから企業にとって有益となるようなエピソードを取り入れ積極的にPRすることが大切ですが、公務員試験ではそれに加えて一番苦労したことを「どう乗り切ったのか」が質問されることがあります。
苦労したことについて、どのように考え工夫をして解決したのか、その過程を知りたいのです。積極的な自己PRと併せて、問題を解決する能力も示せると良いでしょう。
質問事項④:自分から見て長所と短所はなんですか?
これも公務員試験の面接でよく質問される内容です。
短所については、あまりネガティブな要素が強いと合否に影響が出てしまうのではないかと不安になりますが、「短所は長所と裏表の関係にある」ということに気を付けて、性格に一貫性を持たせられると良いでしょう。
また、短所をカバーできるような工夫や対策なども盛り込んで話せるとベターです。
質問事項⑤:学校では何を学びましたか?
公務員試験の面接でこういった質問を受けた際は、専攻で勉強しことを詳しく述べるというよりも、自分が勉強したことを「第三者にわかりやすく伝えることができるかどうか」がチェックされます。
また、「勉強して学んだことを公務員になってからどのように活用していきたいと思っているか」も答えられると良いでしょう。
なお、このほかにも「ストレス解消法はなんですか?」、「待ち時間は何を考えていましたか?」などさまざまな質問をされることが考えられます。
大手予備校などから出版されている公務員試験用の質問&解答対策本を参考にして準備しておきましょう。
特に、技術職ではさらに専門的な質問を受ける可能性が考えられます。
集団面接・集団討論対策

公務員試験で集団面接や集団討論が行われる場合がありますが、どのような流れで行われるのか、またどのような内容となっているのかを知って、事前に対策をとっておきましょう。
公務員試験の集団面接対策
公務員試験での集団面接は、複数人の受験者に対して複数人の面接官が質問する形式で行われます。集団面接が行われるには、主に次のようなふたつの理由が考えられます。
- 受験生を比較検討しやすくするため
- 受験生が多いため個別面接の時間が取れないため
個別面接では一人ひとりにじっくりと質問をすることができますが、ほかの受験生と比較検討することは難しいです。
しかし、集団面接を行って一度に同じ質問を投げかけることができれば、複数の受験生を比較しながら面接することができます。
また、単に受験生の人数が多く個別面接を行うには時間が足りない場合も集団面接が行われるケースもあります。
集団面接で質問される内容は、個人面接での質問と比較して、答えに困るような難しい質問にはならないことが多いです。
ただし、ほかの受験生と比較しやすいため、立ち振る舞いや声の大きさなどが一目でわかってしまいます。
質問に答える内容はもちろんのこと、身だしなみやマナーなども十分に注意したいところです。
公務員試験の集団討論対策
公務員試験の集団討論は、グループに分けられ問われた課題について討論する形式の面接です。グループの人数は5~10人程度、制限時間は40分や60分、90分などさまざまです。
討論形式は、事前にテーマが提示されてあらかじめ準備していき、当日に各自の意見をプレゼンしてから討論に入るケースや、テーマは当日発表されて集められたメンバーで討論に入るケースなどがあります。
テーマは、環境問題や少子高齢化、教育問題、ワークライフバランス、地域振興などニュースに取り上げられているような時事問題が多く、地方公務員ではその自治体特有のテーマが提示されることもあります。
公務員試験での服装やマナー対策

公務員試験の面接試験では、スーツの着用がマナーとなります。20代の人はリクルートスーツで良いでしょう。
社会人で受験する人はふだん着用しているスーツで色は濃紺やグレーなどが無難です。
シャツにはアイロンをかける、靴を磨いておくことも忘れずに。男性は派手なネクタイを避け、女性は目立つアクセサリーやネイルなどは控えましょう。
また、受験案内にクールビズでも可能と記載されていれば指示に従いクールビズでも良いでしょう。ただし、心配な場合はネクタイを持参すると安心です。
また、面接室への入室・退室時のノックや挨拶などのマナーもチェックされる可能性があるため、失敗しないようマナー本などで確認しておくと良いでしょう。
自然にふるまえるように、日頃から練習しておくことがコツです。
まとめ
公務員試験の面接は個別や集団、討論などの方法がありますが、それぞれ流れや内容が異なるため対策も異なります。
事前にどの面接方法が行われるのかを確認し、想定される質問に回答できるよう、また声の大きさやマナーなどにも注意を払えるよう十分に準備しておきましょう。