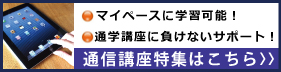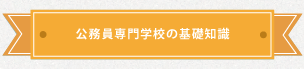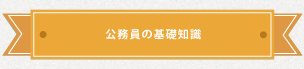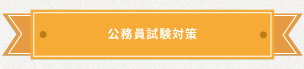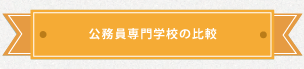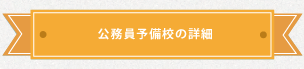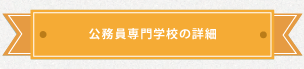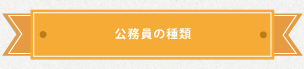2022年公務員試験日程まとめ

就職氷河期に直面している昨今、今年度も公務員試験のシーズンを迎えてきています。
公務員試験に合格するための準備をしっかりした方が公務員試験に合格しやすくなりますね。準備するにあたり、公務員試験の日程を把握しておきましょう。
公務員試験試験には、国家公務員試験と地方公務員試験の2種類があります。ざっくりその2つの違いを紹介すると地方公務員試験は自治体・市役所の職員あるいは教員や消防士、警察官など地域に密着した職業に必要な資格です。
さらに、建築、土木、電気、農業、栄養士や薬剤師などの技術職も含まれます。一方で、国家公務員試験は、国の政策、外交や教育など国の指導で行われる業務を行っているほどの大事な資格です。
これら2つには、特別職と一般職に分かれていることです。
国家公務員試験では、特別職と一般職に分かれていますが、一般職は特別職以外の全てのものを指しており、なおかつ総合職と専門職にも分かれています。
公務員試験といっても多くの種類があるのが分かりますね。
それでは、公務員試験の日程ポイントや流れや選考、日程について一緒に見ていきましょう。
- 目次
公務員試験日程のポイント
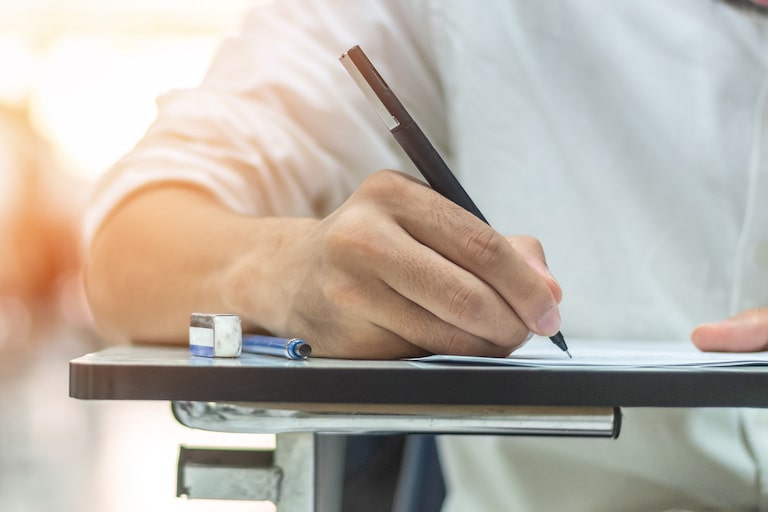
変更点
公務員試験において2021年度から変更点があります。それを以下でまとめました。
①より多くの志望者が公務員試験を受験できるように総合職試験(院卒者試験・大卒程度試験)の申し込み受付の開始日を1週間早め、申し込み受付期間の拡大
②志望者がワントップで多くの公務員試験の採用試験に申し込みができるように、総合職試験(院卒者試験・大卒程度試験)、一般職試験(大卒程度試験)、専門職試験(大卒程度試験)の申し込み受付期間の統一
また、2020、2021年度の公務員試験は新型コロナウイルスの影響によって、公務員試験の日程の変更が相次ぎました。
2022年度の公務員試験も昨年度と同様に日程変更や延期する可能性があるかもしれないので、しっかりと情報を収集して公務員試験を受験しましょう。
公務員試験の日程や変更などの詳細については、人事院ホームページの国家公務員試験採用情報ナビやTwitterなどで情報を得ることが可能かつ正確です。確認ミスで今まで準備してきたことを無駄にしないように気をつけましょうね。
公務員試験の一般的な流れ・選考方法

公務員試験の一般的な流れや選考方法を出願、筆記試験、人物試験、採用という観点から詳しく1つずつ見ていきましょう。
出願
さきに、出願についてです。
公務員試験で出願する際には、インターネットを利用します。インターネット申し込みを行う際に必要なものはパソコン、メールアドレス、Adobe Reader、プリンタです。
スマートフォンでも一部の機種は対応していますが、不具合により申し込みができない恐れがあるためパソコンがおすすめされています。
Adobe Readerは受験票をダウンロードするために必要です。Adobe Readerは無料でダウンロードできるので早めにやっておきましょう。
つぎに申し込みまでの流れを紹介します。パソコンの利用環境をチェックし、大丈夫であったら事前登録および申し込みを行います。
事前登録のためのデータ入力をします。のちに必要になることがあるので、パスワードやパスワードを忘れた際の質問・回答はしっかりと控えておくことをおすすめします。
事前登録完了通知メールを受信したら、申し込みのためのデータを入力し、申し込み受付完了通知メールを受信することができたら申し込みは完了です。
このメールも削除せず保存しておきましょう。申し込みが完了したらパーソナルレコードにログインし、受験票をダウンロードしたのちに受験票を作成しましょう。期間を過ぎてしまうとダウンロードすることができなくなってしまいます。
分からないことや出願に関して不安なことがあれば、人事院のホームページの国家公務員試験採用試験のインターネット申し込みQ&Aを参照してみてください。
申し込み可能期間は以下の通りです。
・院卒者試験・大卒程度試験
国家公務員試験採用総合職と国家公務員採用一般職試験はインターネット事前登録が3月18日~9月5日、インターネット申し込み受付期間が3月18日~4月4日です。受験票ダウンロード期間に関しては、公務員試験総合職が4月12日~4月21日で公務員試験一般職が5月24日~6月9日です。
・高卒程度試験
国家公務員試験採用一般職はインターネット事前登録が院卒者・大卒程度の公務員試験と同様で3月18日~9月5日、インターネット申し込み受付期間が6月20日、受験票ダウンロード期間が8月16日~9月1日です。
受験票ダウンロード期間に関しては制限時刻が設けられているため、そこも把握しておきましょう。
また、受験する公務員試験日程によって、申し込み期間も変わってくるので日程確認を忘れないでください。
筆記試験
筆記試験についてです。
公務員試験の筆記試験には、教養科目と専門科目の2種類に区分されます。この2つをざっくり説明すると教養科目が高校生までに学習する内容で、専門科目が大学の専門課程で学習する内容となっております。
出題形態は、いくつかの選択肢の中から正解を選ぶ択一試験のマークシート方式と与えられたテーマいついて1,000~2,500字程度の文書を書く論述があります。
このように公務員試験には複数種類の試験があります。大阪や主に横浜に当てはまる関東ならではといった全国各地で独自の問題が出題されることがあります。
多くの大卒程度の公務員試験では教養科目がほぼ必須であり、市役所などは選択科目のみで試験が実施されることもあります。他方で、ほぼすべての国家公務員、地方上級公務員や一部の市役所では教養科目と選択科目の両方が出題されます。
では、公務員試験で受ける筆記試験に該当する教養科目について説明します。
教養科目には一般知能と一般知識の2つがあります。それらを1つずつ紹介していきます。
一般知能には、数学的・算術的な思考力や推理力を問う問題で、数的処理、空間把握、判断推理や資料解釈といった数的処理と、英語や現代文、古文や漢文といった国語から本文中から筆者の主張や本文の趣旨を把握するものが中心となっており、与えられた文章に対して、論理的に理解する能力が求められる文章理解の問題が出題されます。
一般知能では、人文科学、自然科学、社会科学と時事に分類することができます。
人文科学
日本・世界史、地理、思想、文学などが出題内容として取り上げられます。
日本史と世界史は両方とも近代史が中心となっています。
地理は自然と人間と世界の地形や気候や土壌が頻出テーマで、思想に関しては西洋の近代思想と日本の思想が出題されやすいです。
文芸は範囲が広すぎてしまい、掴みどころがないのが特徴です。
自然科学
化学、生物や物理などの理科と数学に関係する内容が出題されやすいです。
社会科学
政治、法律、経済や社会関係が出題範囲です。
政治では、政治制度や原理、行政関係や国際関係などと幅広い範囲が出題されます。
経済では、マクロ・ミクロ経済、社会では、社会学・心理学などが問われます。
社会学科の中では、政治と経済が特に出題されやすい傾向があります。
時事
社会保障や労働問題といった現代の日本の重大な政策課題が中心に出題されます。時事問題は他の分野と関連付けて出題されることや記述試験や面接対策としても欠かせない分野になっています。
専門科目も説明します。
公務員試験の専門科目には、法律系、経済系、行政系が出題されます。
行政系の職種では、経済、法律がメインとなりますが、心理職や技術職では各専門分野に対応した専門科目が出題されます。
このように、公務員試験の筆記試験では多ジャンルの知識が必要と分かりますね。
では、公務員試験筆記試験の合格ラインはどれくらいなのでしょうか。
公式に公表はされていませんが、選択択一で5~6割、選択択一で6~7割得点と言われています。
地方公務員試験では教養記述は合否に与える影響力は強いとされているため、しっかりと対策しておきましょう。
基本的には、配点は一般知識が5~7割なので、選択択一対策は、一般知能から取り組むのがベストと言えますね。
5~6月頃に一次試験の筆記試験として専門択一、教養択一、論文試験、専門論文試験が行われます。これを通過することができたら2次の面接試験に進むことができます。
人物試験(面接)
公務員試験筆記試験に合格したら、次は人物試験として口述試験が行われます。個人面接や集団討論を行うことがあります。
近年では、特定のテーマを面接官の前でプレゼンテーションすることもあるそうです。この試験は、7~8月頃に行われます。
採用
二次試験もクリアした方は最後に採用面接があります。
これは、受験生の意識確認を取ることが主であり、併願状況やいくつかの試験に合格した際には、どのような進路を選ぶかどうかなど聞かれます。
以上すべてに合格して、公務員試験を合格し、採用となります。
2022年度試験日程
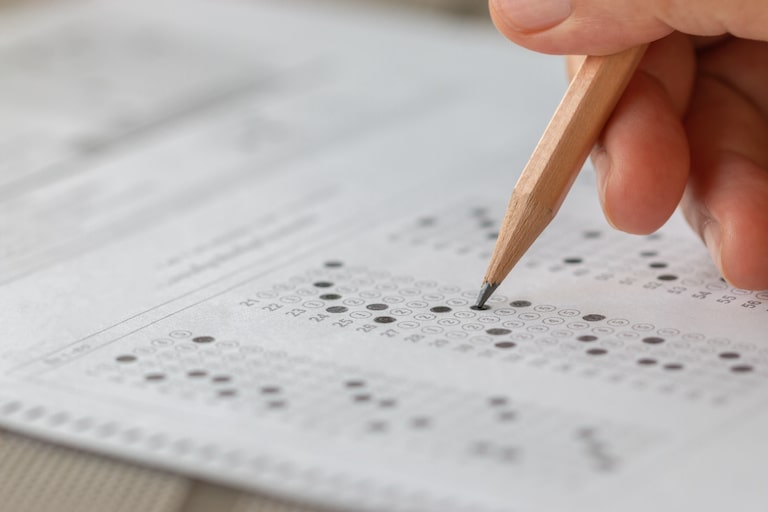
ここで、2022年度公務員試験の日程を一覧で確認しましょう。
国家公務員【大卒程度】
大学卒業程度の国家公務員試験日程を紹介します。
一般試験で申し込み期間が3月18日~4月4日、一次試験が6月12日、二次試験が7月13日~7月29日、最終合格発表が8月16日です。
| 試験名 (職種名) |
申込期間 | 一次試験 | 二次試験 | 最終合格発表 |
|---|---|---|---|---|
| 国家公務員試験 【大卒程度】 |
3月18日~ 4月4日 |
6月12日 | 7月13日~ 7月29日 |
8月16日 |
| 国家公務員試験 【高卒程度】 |
6月20日~ 6月29日 |
9月4日 | 10月12日~ 10月21日 |
11月15日 |
| 地方公務員試験 【大卒程度】 |
4月13日~ 5月18日 |
6月19日 | 7月26日~ 8月10日 |
8月18日 |
| 地方公務員 【中卒程度】 |
7月上旬~ 8月下旬 |
9月25日 | 10月中旬~ 10月下旬 |
11月中旬~ 11月下旬 |
国家公務員【高卒程度】
高卒程度の国家公務員試験日程についても紹介します。
申し込み期間が6月20日~6月29日、一次試験が9月4日、二次試験が10月12日~10月21日、最終合格発表が11月15日です。
地方公務員【大卒程度】
大卒程度の地方公務員試験日程についても紹介します。
今回は川崎市のデータも元にしました。申し込み期間が4月13日~5月18日、一次試験が6月19日、二次試験が7月26日~8月10日、最終合格発表が8月18日です。
地方公務員【中卒程度】
中卒程度の地方公務員試験日程について紹介します。申し込み期間は7月上旬~8月下旬、一次試験は9月25日、二次試験は10月中旬~10月下旬、最終合格発表が11月中旬~11月下旬です。
地方公務員試験の日程は地域・自治体によって異なるため自分が受験する地域の情報を収集しておきましょう。
まとめ
いかかでしたでしょうか。公務員試験の日程、公務員試験の流れ、公務員試験の2022年度試験日程を見ていきました。
色々な種類の試験・試験内容と日程が分かったと思います。
ただ、昨年度の経験から今年度も公務員試験の日程変更があるかもしれません。
日程把握できておらず、受験できないことがないように人事院のホームページをしっかりと確認しましょう。
公務員試験の勉強を独学でするのが不安な方はtacやレックやlecに通って試験対策することをおすすめします。