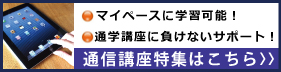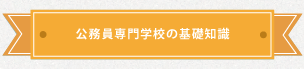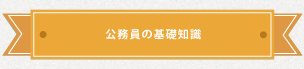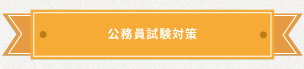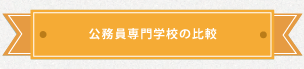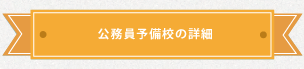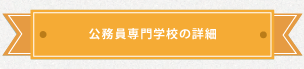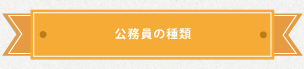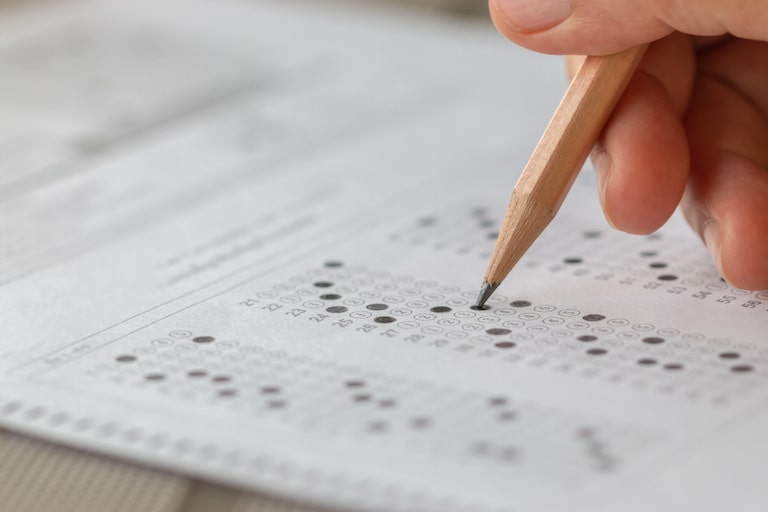
国家公務員・地方公務員(市役所を含む)になるためには公務員試験に合格しなければなりません。計画的に効率よく勉強をすすめていくためには、公務員試験の内容をしっかり把握することが大切です。
ここでは、公務員試験の1次試験・2次試験の具体的な内容を、公務員試験の種類ごとに詳しく解説していきます。また、「高卒程度」と「大卒程度」の違いについても説明しますので、併せて確認していきましょう。
- 目次
公務員試験の基本的な内容
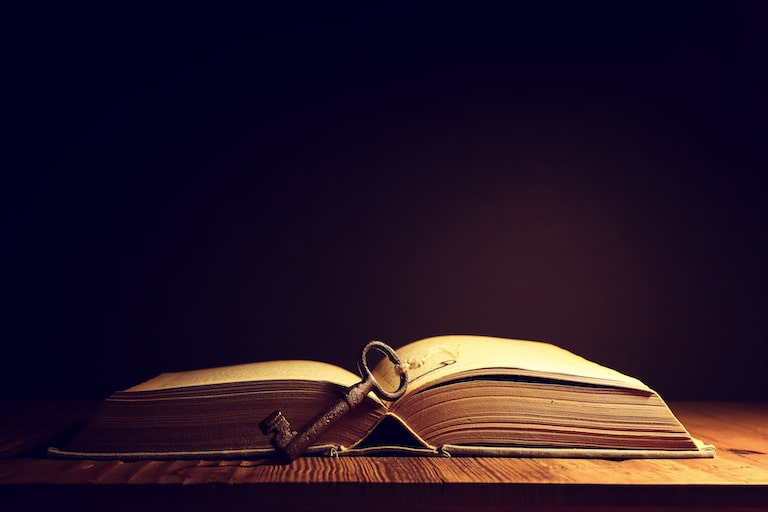
公務員試験の基本的な内容には「筆記試験」と「面接試験(人物試験)」があり、一般的に、1次試験で筆記試験を行い2次試験で面接試験を行うことが多いです。
では、それぞれの試験内容について詳しく確認していきましょう。
公務員試験の筆記試験の内容
公務員試験の筆記試験の内容は、択一式の教養問題と専門問題、論述式の教養論文と専門記述があります。
択一式の教養試験は、ほとんどの公務員試験で出題されており、出題内容は高校で学習することがメインで若干応用問題が加えられています。
なお、公務員試験の教養試験の内容は民間企業での筆記試験と同様なので、公務員試験と民間企業を並行して目指している人は、よりしっかりとした勉強が必要になります。
択一式の専門問題もほとんどの公務員試験で出題されており、主に大学で学習する内容がメインとなります。出題範囲が広いので網羅的に勉強する必要があり、計画的に勉強をすすめることがポイントです。
なお、行政職の場合、政治経済や法律といった分野の問題が出題されますが、経済学部や法学部以外の学生でも十分対応できる内容となっています。
教養論文問題は、一般的に経済問題や社会問題などをテーマに、自分の考えを論文形式でまとめる力が試される内容です。文字数は1,000文字程度であることが多く、事実分析に基づき自分の主張を論理的に述べられるかがポイントになります。
専門記述問題は、国家総合職や外務専門職、裁判所一般職、国税専門官など、国家一般職以外の国家公務員試験で出題されています。
公務員試験の面接試験(人物試験)の内容
公務員試験において面接試験(人物試験)は、近年重要視されている試験項目となっています。面接試験の内容は、一般的に個別面接が行われることが多いですが、集団面接や集団討論といった形態で行われることもあります。
個別面接の内容は、出願時などに提出したエントリーシートをもとに行われることが多いです。受験者1人に対し3~4人の面接官が対応し、面接時間は1人当たり20~30分程度で行われます。
集団面接の内容も、エントリーシートを元に行われることが多いです。一般的に、3~8人の受験生に対して面接官3~4人が対応し、回答順は端から順番であったり、指名制や挙手制を取り入れていたりするケースなどさまざまです。短時間で簡潔に回答できる能力を試されます。
集団討論の内容は、グループごとに課題について討論し意見をまとめるかたちで行われます。
1グループは5~10人程度に分けられ、受験生の考え方はもちろんのこと、社会性や協調性、指導性などもチェックされます。
職種ごとの試験内容
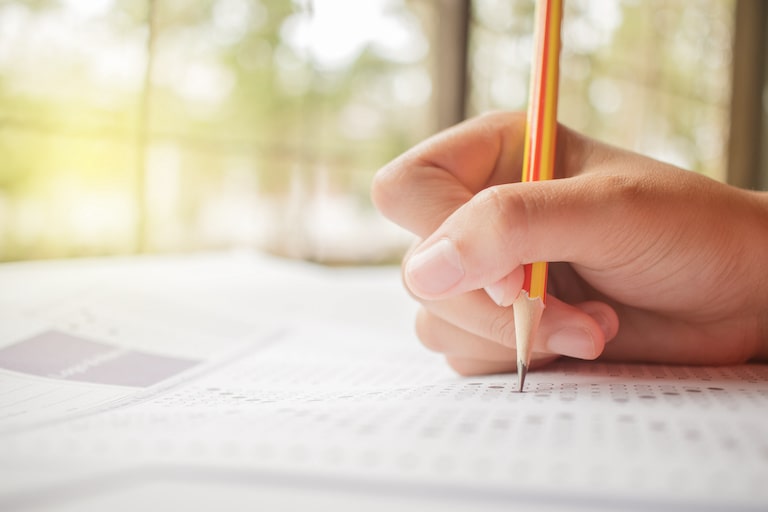
公務員試験とひと言でいっても、さまざまな職種がありそれぞれ試験内容が異なります。そこで、職種ごとで行われている試験内容について一覧表にまとめてみました。
国家公務員の職種ごとの試験内容
国家公務員試験の職種ごとの出題内容は以下のとおりです。
| 職種 | 教養試験 (択一) |
専門試験 (択一) |
教養論文 | 専門記述 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合職 (法律・政治・経済) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 総合職 (教養) |
〇 | - | 〇 | - | 〇 |
| 外交官 (外務専門職) |
〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 国税専門官・財務専門官 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| 労働基準監督官 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
| 一般職 (大卒) |
〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 |
| 裁判所 (一般職) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
択一式の教養問題はすべての職種の試験内容に含まれていますが、ほかの試験項目は職種ごとに異なっていることがわかります。
地方公務員の職種ごとの試験内容
地方公務員試験の職種ごとの出題内容は以下のとおりです。
| 職種 | 教養試験 (択一) |
専門試験 (択一) |
教養論文 | 専門記述 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地方上級 (政令指定都市を含む) |
〇 | 〇 | 〇 | 自治体による | 〇 |
| 市役所 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 |
| 東京都1類B | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 東京特別区 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 |
地方公務員の試験内容は、択一式の教養試験と教養論文がほとんどの職種で行われており、専門試験は択一式・記述式を問わず職種により対応が異なることがわかります。
教養試験の出題科目とその傾向

教養試験は、国家公務員試験・地方公務員試験いずれでも出題されるため、公務員試験を受験する人はだれでも勉強する必要があります。
そこで、教養試験の出題科目と、その出題傾向について解説していきます。
公務員試験の教養試験科目①:一般知能
公務員試験の教養試験科目には「一般知能」があり、さらに細かく「数的処理」と「文章理解」のふたつの科目で構成されています。
数的処理
数的処理は、数学的な思考力や論理性、事務処理能力をはかるための問題内容で、数的推理、判断推理、空間把握、資料解釈の4つの内容で構成されています。択一式の教養試験の3~4割を占めており、最も多くの問題が出題されている科目です。
文章理解
文章理解は、現代文と英語文が中心に出題されており、一部の職種では古文(漢文)が出題されることもありますが出題数は少ないです。教養択一の中では、文章理解は数的処理の次に多く出題されるため十分な勉強が必要になります。
公務員試験の教養試験科目②:一般知識
公務員試験の教養試験には「一般知識」の科目もあり「人文科学」、「自然科学」、「社会科学」、「時事問題」の4つの分野で構成されています。
人文科学
人文科学は、日本史や世界史、地理、文芸・思想といった、高校までに勉強した日本史、世界史、地理、思想文芸の内容から出題されます。広範囲にわたる内容ですが、公務員試験ではわずか1~3問程度しか出題されないため、多くの勉強時間をかけるのはおすすめできません。難易度は、センター試験よりも若干易しめ程度です。
自然科学
自然科学分野では、数学、物理、化学、生物、地学といった中学や高校で勉強した内容が出題されます。そのため、理系の方が有利というわけではなく、高校までの復習程度の勉強で対応できるといえます。
社会科学
社会科学分野では、政治、経済、法律、社会、国際など、中学の「公民」や高校の「現代社会」の内容から出題されます。中でも、政治や経済は出題数が多い傾向があり、法律は憲法の条文に関する知識が問われます。
ただし、社会科学の内容は専門科目の政治、経済、行政、法律、社会など重複しているため、公務員試験の専門科目でもこれらの科目が出題される人にとっては得点源になる可能性がある科目です。
時事問題
時事問題は、実務でも必要になる知識ということもあり出題数が多い傾向があります。社会保障や労働問題、消費者問題、環境問題など、重要な政策課題についての知識が必要です。
また、公務員試験の論文対策や集団討論の際にも役立ち、民間企業も検討している場合にも必要な内容です。日頃から時事問題を意識して勉強に取り入れましょう。
公務員試験での各科目の出題数
公務員試験のうち、教養科目はどのくらい出題されるのか見ていきましょう。国家公務員試験(一般)、地方上級(大卒)、市役所を例に以下にまとめてみました。
| 国家公務員 (一般) |
地方上級 (大卒) |
市役所 | |
|---|---|---|---|
| 数的処理 | 16問 | 16問 | 13問 |
| 文章理解 | 11問 | 9問 | 7問 |
| 人文科学 | 4問 | 7問 | 7問 |
| 自然科学 | 3問 | 7問 | 6問 |
| 社会科学 (時事問題含む) |
6問 | 11問 | 7問 |
| 合計 | 40問 | 50問 | 40問 |
いずれも、数的処理のウェイトが大きいことがわかります。
なお、自治体によって一般知識の出題数や出題範囲は異なることがありますので、必ず受験する自治体の公務員試験要綱などを確認してください。
教養試験の対策方法

公務員試験に合格するためには、教養試験対策が重要です。では、教養科目はどのように勉強をすすめていけば良いのか、対策のポイントを解説します。
教養試験対策①:一般知能
教養試験での一般知能分野は、公務員として勤務する際に必要な事務処理能力を問う問題となっています。
そのため、一般知識分野よりも出題数が多い公務員試験が多く、早い段階から対策を取る必要があります。
一般知能分野の中でも、「数的処理」や「文章理解」は優先的に勉強時間を取ると良いでしょう。
というのも、出題数が多く解き方のコツをつかむのに時間がかかることが多いためです。解法のテクニックが理解できたら、より短時間で解けるように何度も演習を行いましょう。
また、時事問題は教養記述試験や面接試験にも必要な知識となるため、日ごろからニュースなどをチェックしたり直前期にまとめて学習したりして、情報を整理すると良いでしょう。
教養試験対策②:一般知識
教養試験の一般知識分野では、公務員として必要とされる一般的な知識や教養を問われます。出題レベルは大学入学共通テスト程度で、暗記で対応できる問題が多いです。
一般知識分野は、一般知能分野と比較して出題科目が多いにもかかわらず、1科目あたりの出題数が少ないため、すべての科目に均等に力を入れて勉強するのはおすすめできません。
それぞれの科目の頻出項目を中心に、効率よく学習をすすめていくと良いでしょう。
一般知能分野を優先しつつも、一般知識分野も全体的に知識を得られるようスケジュールを立てることがポイントです。
教養試験対策③:過去問を何度も解くことが大事
公務員試験の教養試験では、とにかく過去問を何度も解くことが大事です。何度も繰り返し解くことで、出題傾向がわかったり解法のテクニックなどを習得できたりするようになります。
問題を「解く」というよりも「読む・覚える」というイメージで取り組むのもひとつの方法です。
公務員試験の専門試験の出題科目と傾向
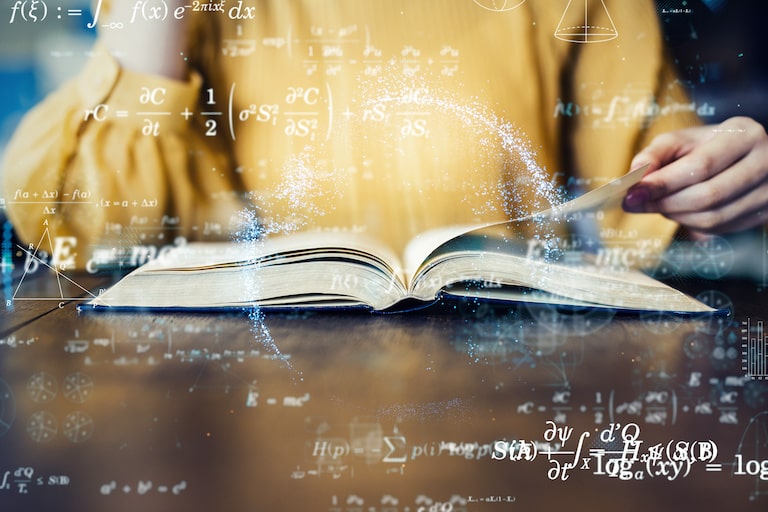
公務員試験では、ほとんどの国家公務員(大卒)と地方上級試験、政令指定都市で択一式の専門試験が行われます。専門試験の出題科目と傾向を確認していきましょう。
公務員試験の専門試験の出題科目
公務員試験の職種によって出題科目が異なりますが、一般的に以下の科目が出題範囲となっています。
| 科目系統 | 出題科目 |
|---|---|
| 法律 | 憲法、民法、行政法、労働法、刑法、商法 |
| 経済 | ミクロ経済学、マクロ経済学、財政学、経済事情 |
| 政治 | 政治学、行政学、社会学、社会政策、国際関係論 |
| 上記以外 | 経営学、会計学、統計学 |
| 人間科学 | 心理学、教育学、社会福祉、社会調査 |
| 技術 | 土木、建築、電気、機械など |
行政職では法律や経済といった科目が多く出題され、人間科学系の職種では心理学や社会福祉学、教育学など各専門分野の科目が多く出題されます。同じく、技術職では土木や建築、機械などの専門科目の勉強が必須です。
必須解答と選択解答がある
公務員試験の択一式の専門試験は、必須解答するものと選択解答するものがあり、さらに選択解答には「科目選択型」と「問題選択型」のふたつがあります。
たとえば、国家一般職の専門試験は40問を解答することとされていますが、問題は16科目(それぞれ5問ずつ)の中から8科目(40問)を選択して解答します。
一方、地方上級(大卒)では科目によって出題数が異なりますが、全問解答することとされています。
職種により出題スタイルが異なりますが、重複する内容も多いため、どの職種を選んでも対応できるような科目に絞って勉強をするのもひとつの方法です。
地方初級(高卒程度)の試験内容

地方初級公務員試験は、地方公務員や政令指定都市の高卒程度のことをいい、地方初級(高卒程度)、高卒者、3類、3種などともいわれています。
地方初級公務員試験の試験内容は、教養試験と作文が行われることが多いですが、教養試験のみを行う自治体もあり試験内容がそれぞれ異なっています。
地方初級公務員試験の1次試験の出題科目
地方初級公務員試験の教養試験は、地方公務員試験(大卒)と同じように一般知能と一般知識、時事問題から出題されます、ただし、自治体により内容が異なるため公務員試験要綱などで確認する必要があります。
主な出題科目は以下の通りで、基本的に択一式での解答となります。
| 出題科目 | 内容 |
|---|---|
| 数的処理 | 判断推理、数的推理、資料解釈 |
| 文章理解 | 現代文、英文 |
| 人文科学 | 日本史、世界史、地理、文学・芸術、思想 |
| 自然科学 | 物理、化学、数学、生物、地学 |
| 社会科学 | 政治、経済、社会、法律、国際 |
高卒程度の学力があることが求められるので、高校卒業までに勉強した内容を理解しているかどうかが問われます。
地方初級公務員試験の2次試験(面接)
地方初級公務員試験の2次試験は、一般的に面接試験が行われます。自治体によって、個別面接のみのところや個別面接と集団面接を行うところなどさまざまです。願書提出時にエントリーシートも提出し、その内容をもとに面接が行われます。
公務員試験の「高卒程度」と「大卒程度」の違い
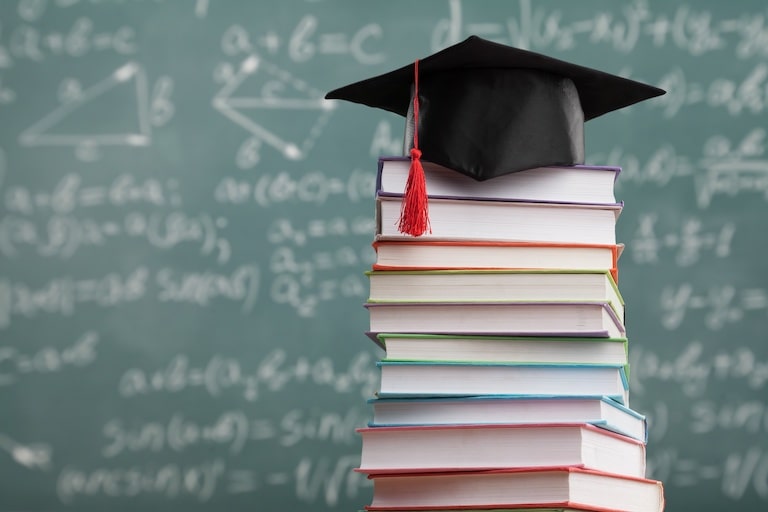
公務員試験には「高卒程度」と「大卒程度」という基準がありますが、これらはどのような意味を持っているのでしょうか。
実は、高卒程度も大卒程度も、必ずしもそれぞれの学校を卒業していることが条件となっているわけではありません。つまり、実際に高校を卒業していなくても高卒程度の学力があれば公務員試験の高卒程度を受験することは可能です。
同じように、大学を卒業していなくても大卒程度の学力があれば、高卒の人でも大卒程度を受験することができるのです。
そのため、一度民間企業に就職したものの、やはり公務員試験を受験したい人は、年齢条件などを満たしていれば民間企業を中途退職し公務員試験にチャレンジすることができます。
公務員試験の高卒程度と大卒程度では、主に1次試験の筆記試験の内容に違いがあります。例として、国家公務員試験(一般職)の高卒程度と大卒程度の試験内容を以下にまとめました。
| 高卒程度 | 教養試験、作文 |
|---|---|
| 大卒程度 | 教養試験、専門試験、論文 |
国家公務員試験(一般職)の高卒程度では教養試験と作文が行われる一方、大卒程度では教養試験のほかに専門試験が行われ論文試験も行われます。このように、試験内容に大きな違いがあり大卒程度の方が難易度が高くなっています。
まとめ
公務員試験の内容は、公務員の職種によってさまざまですが、基本的には1次試験で筆記試験を、2次試験で面接を行うことが多いです。筆記試験では択一式の教養試験や専門試験のほか、専門記述試験や論文といった内容の試験も行われます。
ただし、職種だけでなく自治体によっても試験内容が異なるため、自分が受験する公務員試験の試験内容をしっかりと把握することが大切です。