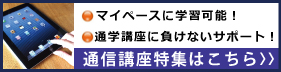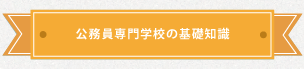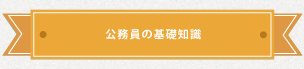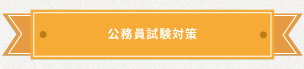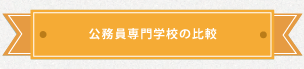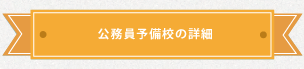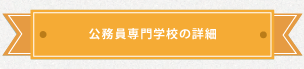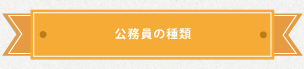公務員試験受験対策で必要不可欠!模試のおすすめ活用法を紹介

公務員試験を受験する際には、大手予備校などで実施されている公開模試を活用するのがおすすめです。公務員試験の公開模試を受験することで、試験の雰囲気に慣れたり時間配分の感覚をつかめたりできるようになります。
この記事では、公務員試験の公開模試を受けることのメリットやおすすめの公開模試などを詳しく紹介していきます。
- 目次
公務員試験の公開模試を受験するメリット

公務員試験を受ける前に公開模試を受験することには、次のような3つのメリットがあります。
公務員試験の公開模試のメリット①:時間配分の感覚がつかめる
公務員試験の公開模試を受けると、試験時間の配分の感覚がつかみやすくなるというメリットがあります。特に、公務員試験の教養問題は、広い分野からたくさん出題されるので、難しい問題に時間をとられ配分を間違えると点数につながらないことがあります。
公開模試で時間内にどの位のペースで解答すれば良いかの感覚をつかんでおくと、本番の公務員試験でも生かすことができます。
公務員試験の公開模試のメリット②:現在のレベルや弱点を把握できる
公務員試験の勉強をしていると自分の中に知識は増えていきますが、受験生の中で自分はどのくらいレベルなのかについては、公開模試を受けなければわかりません。
公開模試を受けて自分の現在のレベルがわかると「次はもっと上位をめざそう」といったように、モチベーションアップにもつながります。
また、公務員試験の公開模試で自分の苦手分野や弱点がわかるので、日ごろの勉強に取り入れることができます。
公務員試験の公開模試のメリット③:計画的に学習がすすめられる
公務員試験の公開模試は、1回だけでなく数回の日程にわけて行われることがほとんどです。
また、ひとつの予備校ではなく複数の予備校を利用すると、日程に合わせてより多くの公開模試を受けることができるでしょう。定期的に公開模試を受ける予定にすれば、「次の公開模試までにはここまで勉強しよう」と計画的に勉強がすすめられるので、公開模試を学習計画に取り入れるとメリハリをつけられます。
「会場受験」と「自宅受験」がある

公務員試験の公開模試には、予備校など所定の場所で行われる会場受験と、会場まで出向かなくても受けられる自宅受験があります。
会場受験での公務員試験の公開模試
会場受験の公務員の公開模試は、申込先から指定された会場に出向き、本番の公務員試験のようにほかの受験生と同時に公開模試を受けます。会場まで出向く手間はありますが、試験会場の雰囲気を感じることができたり、試験慣れできたりするメリットがあります。
大手予備校が主催となる公務員試験の公開模試は、予備校が試験会場になることもありますが外部会場になることもあります。
自宅受験での公務員試験の公開模試
公務員試験の公開模試の受験会場まで出向くことができない人や遠方に住んでいる人などは、自宅受験可能な公務員試験の公開模試に申し込みをすると良いでしょう。自宅受験を選択した場合、問題用紙と解答用紙が送付されるので、自分で時間を計って問題を解いていきます。
終了後は公務員試験の公開模試を実施している団体へ答案用紙を返送し、後日試験結果が送付されるのを待ちます。
2022年・2023年おすすめの公務員試験模試6社

おすすめの公務員試験の公開模試を6社紹介します。いずれも、大手資格予備校や公務員試験対策の講座が充実しているところです。
なお、すでに特定の資格予備校を利用していて、そのカリキュラム内の公務員試験の公開模試を受ける場合でも、日程が合えばほかの資格予備校などで開催している公開模試を受験することをおすすめします。
というのも、各資格予備校で予想問題が異なるため、より多くの問題に触れるとさまざまなパターンの問題に出会えるからです。
おすすめの公務員試験の公開模試①:LEC東京リーガルマインド
LEC東京リーガルマインドの公務員試験の公開模試は幅広い職種に対応しています。実際の公務員試験と同じ制限時間で行われるため時間配分の感覚をつかみたい人におすすめです。全国38拠点での会場模試のほか自宅模試も選択できます。
対応している公務員試験は以下の通りです。
- 国家総合職
- 地方上級・国家一般職・市役所
- 理系(技術系)
- 心理・福祉系
- 警察官・消防官(大卒)
- 経験者採用/高卒程度公務員
料金は各職種によって異なりますが、たとえば「地方上級・国家一般職・市役所」なら1回あたり5,100円(Webの場合4,900円)です。
おすすめの公務員試験の公開模試②:東京アカデミー
東京アカデミーの公務員試験の公開模試は、これまで30年以上にわたり公務員試験受験者に選ばれ続けています。受験者にとって「良質な問題による良質な模試」を提供するために、時間をかけて問題を作成しています。
東京アカデミーで対応している公務員試験の公開模試は以下の通りです。
- 公務員共通
- 警察官・消防官型
- 裁判所職員一般職型
- 国税専門官型・財務専門官型・労働基準監督官A型
- 国家一般職型
- 地方上級型
- 役所型
公開模試にかかる料金は各試験によって異なりますが、国家一般職型模試では、基礎能力試験のみで3,100円(3,600円)、基礎能力+専門試験で4,100円(4,600円)、一般論文試験が1,100円(1,100円)です。
※()内は自宅受験時の料金
おすすめの公務員試験の公開模試③:資格の学校TAC
資格の学校TACの公務員試験の公開模試も多彩な職種に対応しています。
また、「2022年合格目標各種本科生」コースを受講している人は、受験発行手続きをするとカリキュラムに含まれている公開模試を無料で受験することができます。資格の学校TACで受けられる公務員試験の公開模試は以下の通りです。
〇 国家公務員試験
国家総合職/外務専門職/国家一般職(行政・技術職)/裁判所一般職(大卒)/国税専門官/財務専門官/労働基準監督官A
〇 地方公務員試験
東京都Ⅰ類B(行政・技術職)/特別区(事務・技術職)/地方上級/市役所上級
〇 警察官・消防官
警視庁警察官Ⅰ類/警察官(大卒)/東京消防庁消防官Ⅰ類/消防官(大卒)
料金は職種ごとに異なりますが、地方公務員試験(東京都Ⅰ類B/特別区/地方上級/市役所上級)では1回6,600円、5回セットで26,000円です。
おすすめの公務員試験の公開模試④:実務教育出版
実務教育出版の公務員試験の公開模試は、自宅受験のみとなっており、自宅でありながらも本番と同じような実戦練習が可能です。また、公開模試の日程を過ぎてしまっても受験したいという人は、「自己採点セット」も申し込みができます。
実務教育出版の公務員試験模試は以下の職種に対応しています。
- 地方上級公務員
- 国家一般職大卒
- 警察官・消防官(大卒程度)
- 市役所上級公務員
- 高卒・短大卒程度公務員
- 警察官・消防官(高卒程度)
料金は職種により異なりますが、国家一般職大卒コースでは教養のみが3,700円、教養+専門が5,100円です。
おすすめの公務員試験の公開模試⑤:資格の大原
資格の大原の公務員試験の公開模試も公務員試験の職種別に用意されており、志望先に合わせて苦手分野の克服ができるうえに、記述式の解答スキルを身につけることができます。頻出問題だけでなく新傾向問題も取り入れ、厳選したオリジナル問題で構成されています。
資格の大原の公務員試験模試は以下の職種に対応しています。
- 国家⼀般職
- 国税専⾨官
- 裁判所⼀般職
- 地⽅上級
- 東京都Ⅰ類B
- 特別区Ⅰ類
- 警察官・消防官(⼤卒程度)
- 地⽅初級・国家⼀般職
- 警察官・消防官(⾼卒程度)
料金は四角の大原に直接確認してください。なお、高校生には無料で受験できる公開模試が用意されています。
おすすめの公務員試験の公開模試⑥:産経新聞社
産経新聞社の公務員試験の公開模試は、年間15,600人の受験者数を誇る公開模試で、自宅で時間があるときに受験することができます。
また、すでに日程が経過してしまった公務員試験の公開模試を受けたい人向けに、バックナンバー自宅受験も用意されています。産経新聞社の公務員試験の公開模試は、以下の職種に対応しています。
- 国家一般職大卒
- 地方上級
- 市役所上級
- 大卒程度警察官・消防官
料金は、教養のみで4,400円、教養+専門で6,600円です。
公務員試験模試についてのQ&A

公務員試験の公開模試の受験を検討していると、疑問点や不安点などがでてくるものです。ここでは、よくある疑問・不安について回答していきますので参考にしてください。
Q. 公務員試験(高卒程度)も模試を受けた方が良い?
A. はい、できれば模試を受けることをおすすめします。公務員試験には大卒程度だけでなく高卒程度の模試もありますので、時間配分の感覚をつかむためにもぜひ活用しましょう。
Q. 「教養だけ」または「専門だけ」を受けることはできる?
A. 多くの公務員試験の公開模試では、「教養のみ」もしくは「教養+専門」という形式で行っています。そのため、専門だけが可能かどうかは模試の主催団体に確認することをおすすめします。
Q. 模試には論文もある?
A. コースによってあります。論文や作文は添削もしてもらえるので、返却された回答を復習すると次回に活かすことができます。
まとめ
公務員試験の公開模試を受けることで、現在の自分のレベルがわかったり時間配分の感覚がわかったりといったメリットがあります。大手資格予備校などでは本試験まで何回も公務員試験の公開模試が実施されていますので、日程を確認しできるだけ多く申し込みができると良いでしょう。